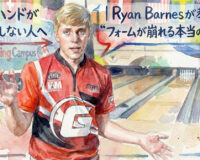マーク・ベイカー最新インタビュー
ドリフト矯正からツーハンドの極意まで、“生ける伝説”の最新ティップス
記事に入る前に、音声による要点解説をお聞きいただくと、内容が一段と理解しやすくなります。
要点音声解説
本要点音声解説は、「The Clean Up Crew」掲載の動画内容を整理・補足して、NotebookLM を用いて生成したものです。
ボウリング界の“生ける伝説”ことマーク・ベイカー氏が、視聴者から寄せられた質問に答える特別インタビューが公開されました。今回のテーマは、ドリフト矯正・ツーハンドの腕の使い方・プッシュアウェイの基本・ターゲティング練習法など、すぐに試せる内容が満載。初心者からプロ志望者まで、すべてのボウラーにとって学びの多い時間となりました。
【1】ドリフト矯正の近道:「スライド地点」から逆算する
ボウリングにおいて「狙ったところに投げたつもりなのに、右に大きく流れてしまう」という悩みは、多くの中級者が直面する壁のひとつです。これを「ドリフト」と呼びますが、マーク・ベイカー氏はこの問題を解決する最短の方法として「スライド地点から逆算するアプローチ」を提案しています。
■ 立ち位置だけ変えても意味がない
多くの人は、「右に流れるなら、最初から左に立てばいいのでは?」と考えがちです。しかし、これでは根本解決になりません。なぜなら、歩き方(アプローチ)の中で身体が横に流れてしまえば、結局ボールの軌道は狂い、正確なコントロールができなくなるからです。
実際、スイングが足にぶつかったり、身体のひねりが大きくなったりすることで、狙い通りの回転やリリースができず、毎回「引っ張るような投球」になってしまいます。
■ 解決の鍵は「スライド地点」の固定
マークが最も重視しているのは、「どこでスライドするか」をまず決めて、そこから逆算して立ち位置と狙い(ターゲット)を調整することです。たとえば、
左足を20枚目にスライドさせる
視線は12枚目を狙う
アームスイングは10〜12枚目の間を通す
というように、「スライド → 通す板 → 視線」という順にロジックを組み立てます。
この順序を逆にして、「最初に狙いを決めてから立ち位置を合わせる」というスタイルでは、アプローチ中の軌道が安定せず、ドリフトに気づかないままフォームを崩してしまうケースが多いのです。
■ 自分だけでは気づけない、だから「付き添い」が重要
多くのボウラーが、自分のドリフトに無自覚であるのも問題のひとつ。そこでマークは、「誰かに横についてもらい、歩行の軌道をチェックしてもらう」ことを強く推奨しています。具体的には、歩き始めてからどのタイミングで横にズレるのか(1歩目か、3歩目か)を外から見てもらうのです。
付き添いの人には、「あなたは25枚目でスライドするつもりで歩いてください。右に入り込んでいきそうになったら、軽く押し戻します」とお願いして、真っ直ぐ歩く感覚を身体に覚えさせます。
■ 練習法:体に“真っ直ぐ”の感覚を刷り込む
マークの推奨する練習法は非常にシンプルですが、効果的です。左足を20枚目に置き、10枚目を視線のターゲットに設定。そして、付き添いと一緒に4〜5投繰り返すことで、「ドリフト0」に近づく感覚が掴めてきます。
目安となるフォームの完成形は以下のとおり:
20枚目でスライド
視線は10枚目
アームスイングは12枚目あたりに垂直に落ちる
頭は常にターゲットの左側に保つ
このフォームで投げると、体とボールのバランスが整い、自然に前方へボールが“まっすぐ出ていく”感覚が得られるようになります。
【2】ツーハンドの核心:「腕は緩く、スイングは高く」
ツーハンドボウリングが世界のトップシーンで主流となって久しく、多くのボウラーがこのスタイルに挑戦しています。しかし、「ボールをどう持つか」「腕の使い方はどうすべきか」といった基本において、誤解や自己流の癖が根付いているケースも少なくありません。
このセクションでは、マーク・ベイカー氏が語るツーハンドの“本質”――それは「腕のリラックス」と「スイングの高さ(=長さ)」です。
■ よくある誤解:前腕でボールを支えるのは間違い
「ツーハンドは両腕で支えるから、前腕にボールを乗せて安定させるのが正しいのでは?」という質問に対し、マークは明確に「NO」と答えています。
前腕で支えてしまうと、二の腕(上腕二頭筋)や肩に力が入りやすく、腕全体が硬直してしまいます。その結果、スイングの振り幅が小さくなり、バックスイングが“高く”取れなくなります。これは、スピードや回転量、ひいてはピンアクションに大きな悪影響を及ぼします。
■ 理想の形:「手のひらに乗せて“ぶら下げる”」
マークは、ツーハンドにおける理想のボールの支え方を「手のひらに“乗せてぶら下げる”感覚」と表現します。これはまるで、ブランコのようなイメージです。
ボール:子ども
両腕:鎖
肩:支柱
この比喩が示す通り、ボールは手首より下の位置、つまり掌のあたりで“吊るすように”保持することで、腕と肩の動きを妨げず、自然な振り子運動が生まれます。
この振り子こそが、ツーハンド最大の武器である“高く大きなスイング”を生み出す原動力となります。
■ スイングの高さ=投球の再現性と破壊力
ツーハンドでは、ワンハンドと違って片手の“引き”がない分、スイングの高さがスピードと回転を作る最大の要素です。マークは、「左手(補助側)を後方へしっかり引ける“ゆるい腕”が必要」だと強調しています。
逆に言えば、腕が硬直していたり、力が入っていると、この後方動作が制限され、結果としてスイングが低く短くなってしまいます。これでは強いボールが出せず、リリースのタイミングも乱れやすくなります。
■ 実例:ベルモンテとサイモンセンに学ぶ
マークは、自身の有料ビデオシリーズ「Game Changer」の中で、ジェイソン・ベルモンテとアンソニー・サイモンセンという世界トップのツーハンドプレイヤーを比較しています。
興味深いのは、両者がまったく異なるアプローチやリズムを持ちながらも、「同じタイミング地点」に入ってくるという事実です。この“タイミング地点”とは、スライド足がフラットになった瞬間に、ボール(または左腕)が地面と平行な位置にあるという状態。
この精密なタイミングがあるからこそ、スイングは無理なく再現され、ボールの回転と方向性が安定します。
■ 実践のヒント:「肩や腕で“投げる”のではない」
ツーハンド初心者や中級者にありがちなのが、腕の力や肩の回転で“投げよう”としてしまうことです。しかしマークは、「それでは精度も再現性も生まれない」と断言します。
代わりに意識すべきは、「スイングに投げさせる」こと。肩の力を抜き、腕はあくまで“つなぎ”であり、ボールの重みとスイング軌道に身体が“ついていく”感覚が理想です。
これを体得するには、練習中から「腕を締め付けず、脱力する」「補助の腕をスムーズに後方へ運ぶ」ことを徹底しましょう。
■ おすすめ練習法
ミラーワーク:鏡の前で構え、腕が硬直していないかをチェック。肩が上がっている場合はNG。
片手スイング練習:ツーハンドでも、ボールを片手で振る感覚を養う練習を取り入れる。腕を“吊るす”動作の確認に最適。
スイング可動域チェック:バックスイングで腕が耳の後ろまで自然に上がっているかを撮影して確認。
【3】プッシュアウェイ:ゼロではダメ、最小限でOK
ボウリングのフォームで見落とされがちなのが「プッシュアウェイ(Pushaway)」の重要性です。プッシュアウェイとは、投球動作の最初にボールを前方に押し出す動きのこと。これが適切でないと、スイング全体のリズムが崩れ、投球のタイミングや精度、再現性に大きく影響します。
マーク・ベイカー氏は、プッシュアウェイについて「完全にゼロは非推奨。小さくてもいいから、必ず“前に出す動き”が必要だ」と語ります。
■ 「プッシュアウェイなし」の落とし穴
近年、ツーハンドを中心に、プッシュアウェイをほとんど行わないスタイルも見られるようになってきました。しかし、マークはそれに対して慎重な立場をとっています。
「ボールを前に出さず、肩の力だけでスタートしてしまうと、下ろす動作も“自力”になる。その結果、腕が早く降りてしまい、スイングとステップのタイミングがずれて“アーリータイミング(早すぎるタイミング)”になるリスクが高い」
つまり、プッシュアウェイを省略することで一時的にスムーズに感じても、長期的にはフォームが不安定になり、特に重いボールや緊張下ではミスの原因になります。
■ 振り子スイングを生み出すための「きっかけ」
マークの説明は非常に明快です。
「ブランコと同じ。最初だけ少し押してやれば、あとは自動的に“カチ、カチ、カチ”とスイングが始まる。何もしなければ、振り子が動き出さない」
この考えに基づき、マークは「2〜3インチ(5〜7センチ)だけ前に出す、小さなプッシュアウェイ」を推奨しています。それだけでも、ボールが自然に下に落ちてスイングが始まり、体とのリズムが噛み合いやすくなります。
■ スタイル別のプッシュアウェイ活用例
● ワンハンド(親指あり)の場合
ワンハンドでは、ボールの重量を片手で支えるため、バランスよく前方に押し出さなければスイングが偏ります。プッシュアウェイが不十分だと、肩が前に突き出て姿勢が崩れ、回転軸も安定しません。
推奨:肘から先を軽く前に出す。腕全体を伸ばそうとしない。
注意点:肩が上がらないようにする。上半身はリラックス。
● サムレス(親指なし)の場合
サムレスでは、ボールを掌で支えるため、前に押す動作に工夫が必要です。特にトップ選手のトム・ドハティは、「前方でボールを隠すような」プッシュアウェイでバックスイングの短さをカバーしています。
推奨:やや高めのプッシュアウェイで、前方空間を確保。
注意点:親指がない分、押しすぎるとリリースのタイミングが不安定になる。
● ツーハンドの場合
ツーハンドでは、両手でボールを支えるため、プッシュアウェイが軽視されがちですが、リズムの起点として重要です。マークは、両手でボールを持った状態から「体の中心線に沿って前に滑らせるように出す」動作を推奨しています。
推奨:下半身の1歩目と連動する小さな前方移動。
注意点:左手(補助手)が早く離れすぎないようにする。
■ 実践のヒントと練習法
スロー動画で確認:スマートフォンで自身の投球をスローモーション撮影し、ボールが“押し出されて”から“下がる”動きがあるかを確認。
ブランコ練習:ボールを持たずに、手を振り子のように前後にスイング。スタートのきっかけがないと振れないことを体感する。
壁トレーニング:壁に向かってプッシュアウェイだけを繰り返し、前方への“滑らかな押し出し”を体に染み込ませる。
■ 結論:「小さく、でも確実に」プッシュせよ
プッシュアウェイは目立たない動作ですが、スイング全体の流れを決める“最初の一手”です。ゼロでは振り子が始まらず、大きすぎればバランスを崩す。そのため、マーク・ベイカーの提唱する「2〜3インチのミニマルなプッシュ」が最適解です。
とにかく重要なのは、プッシュアウェイ=きっかけ作りだということ。力で始めるのではなく、スイングを“誘導”する感覚で、自然なリズムを生み出していきましょう。
【4】ターゲティングと算数:スライド位置と通す板の関係
「なぜ狙った場所に投げているのに当たらないのか?」——この疑問を持ったことがあるなら、あなたのボウリングに足りないのは“算数”かもしれません。ボウリングにおけるターゲティング(狙い)は、感覚だけでなく、立ち位置・スライド位置・ボールが通過する板の関係を数字で捉えることが極めて重要です。
マーク・ベイカー氏は、このターゲティングを「算数」と呼び、プロとアマチュアを分ける明確なラインとして位置づけています。
■ ターゲティングの基本構造:「前」と「奥」を分けて考える
ターゲティングとは、「どこに向かって投げるか」ではなく、「どこをボールに通過させるか」をコントロールする技術です。
マークは、ターゲットを2つの層に分けて説明しています:
前方ターゲット(アローなど)=自分用の目印
奥のターゲット(ブレークポイント)=ボール用の目的地
例えば、アローで12枚目を狙ったとしても、その延長線上にある奥のブレークポイントが外れていれば、ボールは曲がるタイミングを失い、ポケットを外してしまいます。だからこそ、「前を使って、奥を外さない」が鉄則です。
■ 「スライド位置」と「通す板」の対応関係を数式化する
マークが特に重視しているのは、自分のスライドする位置(=最後の足の位置)と、実際にボールを通す板との間にある“角度”の理解です。
彼の考え方では、以下のような「関係表」を持っていることがプロには共通しています:
スライド25枚 → 通す板は11〜13枚
スライド20枚 → 通す板は8〜10枚
スライド17枚 → 通す板は5〜7枚
これらは一例ですが、自分の「得意な角度」「得意なボールのライン」を把握しておくことで、オイルパターンの変化やコンディションに応じた即時対応が可能になります。
■ 実際のターゲティング例:理想のラインを作る
たとえば、「ボールを8枚目付近でブレイクさせたい」と考えたとします。
この場合、以下のように逆算して組み立てます:
奥のターゲット:8枚目付近(ブレークゾーン)
前方ターゲット:10枚目(アロー)
スライド位置:17〜18枚目
立ち位置:スタンスで20〜22枚目
このように「奥 → 前 → スライド → 立ち位置」と情報を積み上げることで、ボールがどこを通り、どこに曲がり、どこに当たるかを完全にコントロールする設計図が完成します。これが“算数”の力です。
■ プロたちの応用例:フィールとテクの融合
マークが紹介する例として、以下のようなプレイヤーたちが挙げられています:
EJタケット:奥のターゲット管理能力が世界一。前方とスライドの角度を固定し、どんなコンディションでも所定スポットへ届ける。
クリス・バーンズ:スライドブレなし(ゼロ・ドリフト)で、アローを通す精度は“10セント硬貨”レベル。
彼らに共通しているのは、「感覚(フィール)」ではなく、「数値(テク)」でラインを設計していることです。つまり、「今日は12枚を投げよう」ではなく、「自分はスライド位置が20枚のときに、10枚を通す角度が得意」と具体的な数字を持ってプレーしているのです。
■ 練習法:自分の「数字」を作る
ターゲティングの精度を高めるには、練習で以下のような取り組みが効果的です。
● 練習メニュー例
板ごとの通過練習
・スライド位置を固定(例:20枚)
・アローを5〜15枚まで1枚ずつ変えて通してみる
・どの角度が一番安定してピンに届くか記録スライドとターゲットの“セット”を覚える
・スライド20→通す10、スライド25→通す13など
・自分だけの「対応表」をノートにまとめておく奥のターゲット観察練習
・ボールが奥でどこで曲がっているかを確認
・前のターゲットに囚われすぎず、奥で狙い通りかを検証
■ 「見る場所」が変われば、命中率も変わる
マークはまた、「ピンを直接見る“ピン見”は非推奨」と言います。なぜなら、ピンを意識すると顎が上がり、肩線が回ってしまい、腕が内側に引き込まれてしまうからです。
それよりも、アロー(前方ターゲット)に集中しつつ、奥のブレークポイントを意識する。この二重視点がプロレベルのターゲティングには欠かせません。
■ 結論:「感覚」ではなく「自分の数字」を持て
ボウリングは感覚のスポーツでありながら、プロほど「数字」で自分を管理しています。マーク・ベイカー氏が何度も強調するのは、
「誰かが『12枚を投げろ』と言ったから投げるのではなく、“自分の数字”でプレーすることが上達の鍵」
ということです。
初心者や中級者の方も、スライド位置と通す板の関係を“数式”として捉え始めることで、一気にプレースタイルが変わってきます。フォームの安定、投球精度、ライン調整力……すべてが段違いに進化していくはずです。
【5】ツーハンドの進化:バックアップボールを習得せよ
ツーハンドスタイルが世界の舞台で席巻するようになってから、スピード・回転・角度という3要素を自在に操ることができるプレイヤーが増えてきました。だが、それと同時に「限界」も見えてきています。
特にオイルが薄くなったレーンや遅いコンディションでは、ツーハンダーが得意とする大きな回転や強いフッキングが“裏目”に出るケースもあります。そんな状況で注目されているのが、「バックアップボール(逆回転球)」の習得です。
■ バックアップボールとは何か?
バックアップボールとは、通常のフックとは逆方向に回転するボールのことを指します。
右投げの通常フック:右から左に曲がる
バックアップボール:左から右に曲がる(=左利き投手のような軌道)
これにより、通常のフックラインでは対応できない外側からの角度、あるいはオイルの薄い部分を避けたライン取りが可能になります。特にレーンが焼けてインサイドが使えない場面では、大きな武器となる技術です。
■ ツーハンドにおける「新しい引き出し」としての役割
マーク・ベイカー氏は、ツーハンドボウリングの将来像を見据え、「全ツーハンダーの10%の練習時間を、バックアップボールに充てる価値がある」と語ります。
この発言の背景には、オイルコンディションの多様化と、ライン取りの引き出し不足という問題があります。
ツーハンドは本来、回転数が多く角度も鋭いため、オイルが厚く、レーンが長めの環境に適しています。しかし、試合が進むにつれてオイルが削れ、レーンが遅くなってくると、持ち前の強さがかえってコントロールの難しさにつながってしまいます。
そこで、逆回転のボールを覚えることで、ボウラーは以下のような状況に対応可能になります:
ドライな外側レーンを逆手にとって攻める
インサイドが使えない状況で角度を確保
スペアショットでも左右差を打ち消して安定感を出す
■ 世界ではすでに実用段階へ
スウェーデンやドイツをはじめとする欧州の若手選手たちは、バックアップボールを積極的に取り入れています。中には、レブレート500・球速19マイルでバックアップを投げるという選手も登場しており、その精度・威力ともに従来の“実験的技術”の域を超えつつあります。
この進化は、単なるトリックショットではなく、「戦術的武器」として確実に評価され始めているのです。
■ 練習の導入方法:まずは“違和感”を受け入れる
バックアップボールの習得には、通常のスイングとは全く異なる腕・手首・リリース角度の使い方が求められます。最初は「こんな投げ方でいいのか?」という違和感がありますが、それを受け入れることが第一歩です。
● ステップ1:構えとフィンガーの位置を変える
手のひらを少し上向きに構える
通常とは逆側(左方向)に“こねる”ような回転を意識
リリースでは、手首を内側に捻らないようにする(外回転を保つ)
● ステップ2:短い距離からリリース練習
フルアプローチではなく、3歩スタートでボールのリリース感覚を練習
5〜10枚目をストレートに通すつもりで、ボールの“滑り”と“逆回転”を確認
● ステップ3:実戦ラインで使ってみる
ドライなレーンや、バックエンドで早く曲がりすぎるコンディションで実戦投入
通常のラインと比較して、オイルに対する反応や曲がり方を観察
■ スペアメイクへの応用:「安定した右サイド攻略」
特にツーハンダーにとって課題となりやすいのが、右サイドのスペアメイク(例:10番ピン)です。回転が強すぎて抜けやすく、安定性に欠けるという声も多く聞かれます。
このような場面で、親指を入れて投げる“スリー・フィンガー”のスペアボールや、逆回転で曲がりを殺すという発想が効果的になります。
マークは「ピンを直接見る“ピン見”は避け、胸骨(胸の中心)をピンに向けることが重要」とし、胸の向きを安定させることでリリースの再現性を高めるよう指導しています。
■ 練習の一部に組み込む「10%ルール」
マークのアドバイスは明確です:
「全ツーハンダーは練習の10%を、バックアップボールやスペアのための逆回転技術に使うべきだ」
つまり、週に100ゲーム練習するなら、10ゲームはこの逆方向へのスキルに費やす。これにより、通常のラインが効かないときの“逃げ場”が生まれ、トーナメントでの生存力が飛躍的に上がるのです。
■ まとめ:ツーハンドは「回転力」だけでは勝てない時代へ
強烈な回転と破壊力で一時代を築いたツーハンドスタイルも、今や進化の分岐点に差しかかっています。これからは「選べるライン」「削れる角度」「逆も使える器用さ」が問われる時代です。
バックアップボールの習得は、その象徴とも言える技術。ツーハンドであっても、「引き出しの多さ」が勝負を分ける時代が来ているのです。
【6】タイミングのすべて:「体が先、スイングが後」
多くのボウラーが見落としがちな“究極の基本”が、タイミングです。フォームが綺麗でも、ボールの回転が高くても、スピードが速くても、タイミングがズレていればすべてが無意味になる。それほど、タイミングは投球精度・再現性・回転の質・リリースの安定に直結する重要要素です。
マーク・ベイカー氏は、「タイミングが合っていなければ、どんなに素晴らしいリリースも決まらない」と断言しています。
■ タイミングの定義:「スライドが先、スイングが後」
マークの考える理想的なタイミングはとてもシンプルです:
「スライド足が地面にフラットになった瞬間に、ボール(またはツーハンドなら左手)が地面と平行な高さにある」
この状態が、いわば“完璧なリリースの準備位置”です。この瞬間に体が安定し、腕が“投げる準備”を整えた状態で、自然なスイングによってボールがリリースされるわけです。
つまり、「体が先行し、スイングが後からついてくる」ことが重要であり、逆にスイングが先に降りてしまうと、以下のような問題が生じます:
アーリータイミング(タイミングが早すぎてスイングとステップが噛み合わない)
スイングが身体にぶつかる、または引っかかる
ボールが体の横や前でリリースされるため、回転が安定しない
身体の動きが“投げる”側に入ってしまい、脱力したスイングができない
■ ワンハンドでもツーハンドでも「タイミング地点」は共通
興味深いのは、スタイルの違い(ワンハンドかツーハンドか)にかかわらず、マークが定義する「タイミング地点」は共通しているという点です。
例えば、世界のトップ選手——
ジェイソン・ベルモンテ
アンソニー・サイモンセン
フランソワ・ルボワ
カイル・トループ
ヤスパー・スベンソン
彼ら全員が、リリース直前に「スライド足がフラット」「スイングが地面と平行」という同じ“タイミング地点”に、自分なりのリズムで到達しているのです。
それぞれフォームやステップ数、助走のテンポは異なりますが、到達すべきゴールは同じ。それが、どんな状況でもボールを安定して再現できる秘密です。
■ よくある失敗例とその原因
タイミングの乱れは、初心者から上級者までに起こりうる問題です。以下はマークが指摘する典型的なパターンです:
① スイングが先行してしまう
原因:プッシュアウェイが大きすぎる/ステップが遅い/上半身が前に突っ込む
結果:アーリータイミングになり、ボールが早くリリースされすぎる
② スライドが遅れる(レイトタイミング)
原因:スイングを待ちすぎる/ステップが速すぎる/ボールを抱え込んでいる
結果:スライド中にボールが落ちる/体の軸が後傾しやすい
どちらも、「ボールをコントロールしよう」とする意識が強すぎる場合に起こります。大切なのは、スイングに合わせて“体が準備する”という順序を守ることです。
■ タイミングの整え方:感覚ではなく「見るポイント」を変える
マークは、タイミングを整えるために「スイングとステップの同期」を客観的に把握することを提案しています。
● 自撮り動画での確認
スライド足が地面にフラットになる瞬間をチェック
そのとき、スイング(または左手)はどの位置にあるか?
肩が投げ急いで前に出ていないか?
● タイミング練習ドリル
3歩助走ドリル
・スライドを最優先に意識し、最後の1歩に「合わせて」スイングを落とす練習プッシュアウェイを遅らせる練習
・あえてボールの出し始めを0.5秒遅らせ、体との同期を確認
● 感覚の補助ワード
「ボールに引っ張られる」ではなく「体が導く」
「先に歩いて、後ろから腕がついてくる」
「投げる」のではなく「振り子が落ちる瞬間に委ねる」
■ 「ボールの下に残ろう」では直らない
タイミングが狂ってしまった人にありがちなのが、「ボールの下に手を残そう」と意識してしまうことです。これは一見正しいようで、実は結果の修正に過ぎず、原因の解決にはならないとマークは言います。
問題の根本は、「体がスイングを追い越している」ことにあります。つまり、“タイミング”を変えない限り、どれだけ意識しても手は下に残らない。正しくは、
「体が先にスライドし、スイングが後から降りてくる」
→ その自然な順序の中で、手がボールの下に残る
という流れを作ることが、唯一の解決策なのです。
■ タイミングこそ、すべての核
どんなスタイルであれ、タイミングが整っていなければ、精度も再現性も、ボールリアクションも崩れてしまいます。フォーム修正やボール選びの前に、まずタイミング。これがマーク・ベイカーの一貫した哲学です。
■ 練習提案:毎回「タイミングの到達点」を確認する
投球前に「スライドが先、スイングは地面と平行」と唱える
投球後は動画チェック、または他者に位置関係を確認してもらう
タイミングが合っているときは、投球後のフィーリングが軽く、ボールの軌道も安定する
■ 結論:投げるのではない、スイングに“投げさせる”
究極的に言えば、正しいタイミングとは「投げているのではなく、投げ“させている”状態」です。力を使わず、ボールが自然と手を離れていくその瞬間こそが、ボウリングの理想形です。
体が先、スイングが後。その順序さえ守れば、リリースは再現され、ラインは安定し、あなたのボウリングは確実に進化していくでしょう。
まとめ:上達への道は「自分の数字」を持つことから
これまで、マーク・ベイカー氏の豊富な経験と知見に基づいた7つの実践的ティップスを紹介してきました。ドリフト矯正、ツーハンドのフォーム、プッシュアウェイ、ターゲティング、バックアップボール、そしてタイミング。これらの全てに共通しているのは、「感覚だけに頼らず、データ(数字)で自分を理解する」という姿勢です。
マークが何度も強調しているのは、「誰かに言われた通り投げるのではなく、“自分の数字”を知って投げることが、上達の鍵である」という考え方です。
■ 自分の「数字」とは何か?
ここで言う「数字」とは、ボウリングにおいて次のような項目を数値として把握し、再現できるようにすることを指します:
立ち位置(スタンスの板番号)
スライド位置
通す板(アローまたは手前の通過点)
ブレークポイント(奥の曲がり始める地点)
スイングのタイミングと高さ
回転数(レブレート)と球速
ドリフト量(左右に何枚ずれるか)
これらをすべて“自分専用のデータ”として記録・管理していくことで、レーン状況が変わっても、緊張する場面でも、「自分のいつものフォーム」で投げられる再現性が生まれます。
■ 感覚だけでは限界がある
もちろん、ボウリングは感覚のスポーツでもあります。手応え、指の抜け、足のリズム、リリースのフィーリングなど、細かな感覚の積み重ねも大切です。しかし、感覚は環境に左右されやすく、数値は裏切らないというのもまた事実です。
「なんとなく良かった」では調整できない
「曲がらなかった」だけでは原因がわからない
そういった曖昧さから脱却し、自分の数字を持ち、分析できるようになったとき、ボウラーとしてのレベルは一段階上がります。
■ 世界のトップは「データと感覚の融合」で戦っている
EJタケットは、奥のターゲット管理において世界トップクラスと称され、必ず「一定の角度と数値」でボールを目的地に届けます。クリス・バーンズは、スライド板とアローの関係を完全に覚えており、“10セント硬貨”の上を通す精度を持っています。
彼らは天才ではなく、「数字の管理」と「感覚のすり合わせ」を長年続けてきた結果、唯一無二の精度と再現性を身につけたのです。
■ 最初はシンプルなところから始めよう
「自分の数字」と言われると、難しそうに感じるかもしれませんが、最初は以下のような簡単な記録から始めるだけで十分です:
今日の立ち位置:25枚目
通したいアロー:10枚目
ドリフト:3枚右にズレた
スライド位置:22枚目
投げた感触:〇(良い)/△(普通)/×(悪い)
このような簡単な「自己ログ」を数投ごとにメモしていくことで、自分の特徴や癖、修正ポイントが浮き彫りになってきます。
■ 継続こそが、ボウリング上達の最大の武器
プロボウラーのクリス・バーンズは、22歳から50歳まで週平均100ゲーム以上を28年間続けてきたといいます。天才ですらこれだけの反復と継続を重ねているのです。
上達の道に「近道」はありませんが、「正しい道を歩く」ことで確実に結果はついてきます。そのための道しるべが、今回紹介したドリフト矯正、スイングの高さ、プッシュアウェイ、ターゲティング、タイミング、バックアップボールといった各項目であり、これらを支えるのが「自分の数字」なのです。