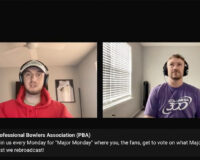祖母の声を胸に、私は進む。
Olivia Farwellのボウリング人生
■ ソフトボール一筋の少女が見た、もうひとつの「道」
子どもの頃からバットとグローブが相棒だった。
Tボールに始まり、リトルリーグ、そして本格的なソフトボールへと進み、ポジションはファースト、打順はクリーンナップの4番。誰もが「彼女はソフトボールのエースになる」と信じて疑わなかった。そして本人もまた、大学でもソフトボールを続ける未来を疑ってはいなかった。
だが、高校の冬、すべてが変わる。
兄・オースティンが高校のボウリング部で活躍していた姿に、ふと心を奪われた。兄のチームが州大会を制覇し、観戦していた彼女の心に何かが灯る。「ちょっとやってみたいかも」。ただの興味だったはずの感情が、確かな選択肢へと変わっていく。
高校のコーチから「君は必ずボウリング部に入る」と言われ続けても、「いいえ、私はソフトボールで大学に行くんです」と笑っていた。だがその冬、ソフトボールのオフシーズン練習とボウリングの州大会予選が重なり、ついに分岐点が訪れる。
コーチからの言葉は厳しかった。
「本気でここに来られないなら、試合には出さない。」
チームメイトとの友情、長年積み重ねてきた実績、捨てきれない愛着——それでも、Oliviaは決断する。
「私は、ボウリングの道を選ぶ。」
涙が出るほど苦しい選択だった。だがその時、彼女の中で確かに何かが始まった。バットを置いた瞬間、新たなレーンが目の前に開けたのだった。
■ 無名の大学チームからの挑戦と成長
ボウリングの道を選んだ彼女が進学したのは、全米の強豪校ではなかった。Duane大学——まだ設立2年目の新設チームだった。世間的な知名度はなく、選手層も決して厚くない。名門校のような設備も、派手な実績もなかった。
だが、Oliviaはあえてその道を選んだ。
「このチームを、私が変える。」
静かに、しかし確かな闘志を胸に、彼女はそのユニフォームに袖を通した。
1年生の頃から、彼女はすでにチームの“軸”だった。スコアだけでなく、声かけ、態度、周囲への気遣い——すべてにおいて、自然とリーダーシップを発揮していった。リクルート活動の手伝いまで担い、学校訪問に来る新入生候補たちと話をしながら、チームの魅力を伝える役割まで任されていた。
だが、そうした責任が重く感じられる瞬間もあった。
「うまく伝えられているのか、私の言葉でこの子たちは入ってくれるのか、そんな不安がいつもあった。」
それでも、彼女は逃げなかった。
「私がこのチームの未来をつくる。」
その想いだけで、目の前の練習や大会に全力で挑み続けた。
成績も伴ってきた。
1年目から安定した実力を見せ、2年目、3年目にはチームとしてのレベルも上がっていった。彼女が率いるDuane大学は、次第に“無名校”という立場から抜け出し、全米にその名を知られるようになる。
「私はいつも、チームのために何ができるかを考えていた。自分の成績以上に、周りをどう引き上げるか。そこに全力だった。」
大学生活の中で、彼女は「勝つ選手」である以前に、「誰かの目標になるリーダー」であることの意味を学んでいった。
ボウリングという個人競技に見える世界で、仲間と共に強くなることの喜びを知った。その原点こそが、後の彼女のプロとしての姿勢、そして「人に寄り添う力」へとつながっていく。
■ 初の全国中継、そしてプロの扉が開く
大学4年生、集大成の年。
Olivia Farwellは、その年の全米学生選手権(ISC)で、ついに全国中継の舞台に立つことになった。あの大舞台、テレビカメラ、観客の視線。そして、全米中のファンが見守る中で、自分の名前が紹介された瞬間、彼女は胸の奥が震えるのを感じた。
「ここまで来たんだ。無名校から、ここまで来られたんだ。」
だが、その大舞台での結果は決して満足のいくものではなかった。
緊張から思うように投げられず、シード5位での出場となった試合は悔しい形で終わる。しかし、その日、結果以上に彼女の人生を大きく変える出来事が待っていた。
観客席にいたJim Callahan――Storm社の代表格的な存在であり、世界のトップブランドのひとつを担う人物――が、彼女の投球を静かに見守っていた。
試合後、Jimはまっすぐ彼女のもとへ歩み寄り、言った。
「これを着けなさい。」
そう言って手渡されたのはStormのパッチだった。
プロの象徴とも言えるそのパッチは、まるで合格証のように彼女の手に渡された。
「えっ、ルール的に着けていいんですか?」と戸惑う彼女に、Jimはにっこりと笑いながら答えた。
「いいんだよ。着けて、行け。」
彼女は言葉に従い、ユニフォームにパッチを付けてステージに戻った。
その瞬間、彼女の中で何かがはっきりと切り替わった。
「私は、ここからプロの世界に入る。」
試合後、Jimからメールが届いた。
件名には「SPI契約のご案内」。本文は驚くほどシンプルだった。
「名前だけ入力してくれればいい。他の項目は気にするな。」
それはまさに、運命のメールだった。
大学卒業後は1年の猶予をもって将来を考える予定だったが、その決意は一瞬で覆された。
「この波に乗らなかったら、きっと後悔する。」
彼女は迷いなくフルスロットルでプロの道へと進むことを決めた。
■ 最愛の祖母、最大の支え
Olivia Farwellにとって、ボウリングのキャリアを語るうえで欠かすことのできない存在がいる——それが、祖母の存在だ。
彼女の人生のすべての節目に、いつも祖母がいた。
土曜日朝のジュニアリーグ。高校の小さな大会。大学の遠征試合。寒い日も、長距離の移動でも、祖母は必ず会場に現れた。そして、スコアがふるわない日でも、満面の笑みを浮かべながらこう言った。
「あなたは最高よ。」
たとえスコアが150点でも、祖母にとっては300点と同じ価値だった。彼女の応援は、数字では測れない、深い愛と誇りに満ちていた。
そんな祖母が、大学4年目の春、体調を崩す。
カンファレンスチャンピオンシップの数日前、家族はすでに祖母のがんの診断を知っていた。だが、Oliviaには言わなかった。大切な試合に集中してほしいという家族の想いからだった。
大会は惜しくも敗退し、彼女が涙をこらえているとき、そっと伝えられた。
「おばあちゃんが、病気なんだ。」
その言葉を聞いた瞬間、全身から力が抜けた。
彼女はすぐにチームと別れ、家に戻った。帰った先は、見慣れたホームセンターのボウリング場。そこにいた祖母は、いつものように明るく笑っていた。
まるで病気などなかったかのように。
「自分のことよりも、まずあなたの気持ちを心配する人だった。」
そう語るOliviaの目には、今もその日の祖母の笑顔が焼きついている。
彼女は泣くのをこらえながら、祖母の隣に座った。
いつも通り、Snapchatでフィルターをかけて、2人でふざけ合って動画を撮った。笑い声の裏で、胸が張り裂けそうだった。だが、祖母が「あなたがいてくれて嬉しい」と言ってくれたその一言が、すべてだった。
その日から、彼女の人生には新たな使命が加わった。
——「祖母が願った舞台で、戦い続けること。」
今、彼女の背中には祖母のイニシャルと2つのハートの刺繍がある。試合中、ふと気持ちがぶれてしまいそうになると、そこに触れ、祖母の声を思い出す。
「大丈夫、あなたならできる。」
「祖母は、今も私の中に生きている。ボールを投げるその一投一投に、彼女の声が重なる。」
祖母が夢見た光景を、Oliviaは今、現実にしている。
勝っても、負けても、そこに彼女の祈りがある限り、Olivia Farwellのレーンには、いつもあの笑顔がそっと寄り添っている。
■ 仲間と支え合いながら進むツアー生活
プロとして本格的にツアーを回るようになってから、Olivia Farwellは新たな“現実”にも直面した。それは、成績だけではない、心の波との付き合い方だった。
ツアー生活は、一見華やかに見えるが、実際は孤独との闘いでもある。
地方都市を巡る日々、ホテルと会場の往復、移動中の長い時間。そして試合で思うようにいかない時、自分自身を奮い立たせるのは簡単なことではない。
そんな中で、彼女を支えたのは“仲間”の存在だった。
ある日、気持ちが沈み、祖母のいない現実が胸を締めつけるように苦しくなった時、ひとりのツアー仲間Danielle McEwanが、ふと何気ない贈り物をくれた。
「これ、持ってて。」
差し出されたのは、小さな天使のキーホルダー。
そこには何の言葉もなかったが、すべてが伝わった。
「Danielleとは当時、そこまで親しい間柄じゃなかった。でもその優しさが、私を救ってくれた。」
そのキーホルダーは、今も彼女のバッグにぶら下がっている。
さらに、彼女は人と接することを何よりも大切にしている選手だ。試合中、他の選手が苦しんでいる様子を見ると、あえてボウリングとは関係ない話題で声をかける。「最近ハマってるドラマって何?」「昨日、ホテルの朝食すごく良かったよ!」——そんな何気ない会話の中に、心をゆるめる瞬間があると知っているからだ。
「笑ってもらえたら、それだけでいい。それが誰かの救いになるなら、私は話しかける。」
Oliviaは、勝ち負けだけを追いかけるアスリートではない。周囲の心を温める存在として、今もツアーの中で信頼され続けている。
■ 初心を忘れず、夢を追いかけて
全国中継、スポンサー契約、プロデビュー——
それらはすべて、彼女の人生のターニングポイントだったが、その根底に流れているのは初心の気持ちだった。
大学時代、初めて出場したPWBAツアーでの出来事。
舞台はペンシルベニア州ハリスバーグ。あの伝説的選手Shannon O’Keefeと同じレーンに立ったとき、彼女は緊張のあまり順番を間違えて投球準備に入ってしまった。
「Shannonと目が合って、“あ、やっちゃった…”って思った。」
慌てて戻り、母の元に駆け寄ると、冷や汗でシャツはぐっしょりだったという。
「この1投が将来の進路に影響するんじゃないか」
「Shannonの印象、悪くしちゃったんじゃないか」
そんな不安が渦巻いたが、後日Shannonと笑いながらその話をしたとき、彼女はまったく覚えていなかった。
「その時思った。自分で思ってるほど、失敗って大きくないんだ。」
プロになった今でも、彼女はその“恥ずかしい思い出”を大切にしている。
なぜなら、その経験があるからこそ、今苦しんでいる若手たちにもやさしく寄り添えるからだ。
「私は常に“人間らしさ”を忘れたくない。」
どんなに成功しても、心は初心のまま。
祖母の笑顔、仲間の支え、初めての失敗——すべてが今のOlivia Farwellを形づくっている。
ツアーの過酷さに心が折れそうな日もある。
けれど、彼女は言う。
「祖母の声が聞こえる限り、私はこの道を走り続ける。」
彼女の夢は、勝利だけではない。
人の心に何かを残せる選手になること——それが、Olivia Farwellの“プロ”という生き方なのだ。
■ 終わりに:祖母が見たかった景色を、今ここで
Olivia Farwellが今、立っている場所は、かつて祖母が心から願っていた場所だ。
それは、テレビ越しに、あるいは観客席から目を細めながら、「いつか、あの大舞台に立つあなたを見たい」と、何度も語ってくれた夢の光景だった。
「おばあちゃん、見ていてくれてるかな?」
大きな会場の照明がまばゆく灯り、観客の視線が集まるレーンの上に立つたび、Oliviaの胸にはそんな想いが去来する。
彼女の背中には、祖母のイニシャルと2つのハートが、静かに、そして確かに刺繍されている。
それは装飾ではない。“共に戦っている”という証だ。
試合中、ふと調子を崩すときがある。
焦り、苛立ち、プレッシャーに押しつぶされそうなとき——
そんな瞬間、心の中で聞こえてくるのは、あの日と変わらない優しい声。
「だいじょうぶよ。あなたなら、できる。」
その声に背中を押されるように、彼女は深呼吸をし、次の一投に集中する。
「次のゲームが、きっと良くなる」。そう信じて立ち上がることができるのは、祖母が彼女に残してくれた心の魔法のおかげだ。
彼女の旅は、まだ始まったばかりだ。
勝利に一喜一憂する毎日の中で、彼女は少しずつ、“ただ強い選手”ではなく、“誰かの希望になれる選手”へと歩を進めている。
若い世代の選手たちに声をかけ、仲間の心に寄り添い、そしてどんなときも笑顔を忘れずにいること。
それはすべて、祖母が教えてくれた「強さ」のカタチだ。
「ボウリングで成功することは、私にとって夢の一部。でも、誰かの心を温められる存在になること、それが本当の意味での“プロ”だと感じています。」
たとえ、もう祖母に会うことはできなくても、彼女の存在は決して消えない。
それどころか、Oliviaの歩みのすべてに、祖母の愛が溶け込んでいる。
だから彼女は、今日もユニフォームを身にまとい、ボールを持ってレーンに立つ。
「ここが、私の居場所。そして、祖母が見たかった景色。」
静かに、力強く、そして心の奥底で誓いながら——
Olivia Farwellは、これからも夢の続きを投げ続けていく。