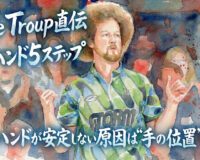マーク・ベイカーのボウリング上達25のヒント
記事に入る前に、音声による要点解説をお聞きいただくと、内容が一段と理解しやすくなります。
要点音声解説
本要点音声解説は、「The Clean Up Crew」掲載の動画内容を整理・補足して、NotebookLM を用いて生成したものです。
プロボウラーであり、世界的に有名なコーチであるマーク・ベイカー氏が、ボウリング技術向上のための25の実践的なアドバイスを紹介しています。初心者から上級者まで、すべてのボウラーに役立つ内容です。
1. 特定のボールだけが指穴を通過する理由
ボウラーの多くが経験する疑問のひとつに、「複数持っているボールの中で、特定の1個だけがフレアリング(軌道のオイル跡)で指穴の上を転がる」という現象があります。これにはいくつかの原因が考えられ、原因を特定するにはボール、投球フォーム、さらにはボールレイアウト(ドリルパターン)の理解が重要になります。
◆ 基本の理屈:フレアとは?
まず理解しておきたいのが「フレア」という現象。これはボールがレーンを転がる際に、コア(重心)とカバーストック(外殻)の特性により、回転軸が少しずつ移動していくことによって起きる、オイルのリング状の跡です。フレアが多いほど、ボールはより多くの回転軸を使っており、その分、ピンに対して鋭く入っていく傾向があります。
◆ 指穴を通るのは「問題」なのか?
フレアが指穴(サムホールまたはフィンガーホール)の上を通ると、そこに摩擦のズレや接触が生まれ、ボールの回転や軌道に悪影響を及ぼすことがあります。しかし、すべてのボールがそうなるわけではなく、「ある特定の1球だけ」がそうなる場合、それはプレイヤーのフォームやリリースよりも、そのボール固有のレイアウトに原因がある可能性が高いと考えられます。
◆ 原因の可能性1:ドリルの配置(レイアウト)
ボールは、同じ型番・同じブランドであっても、コアの向きやドリルの仕方によって性能が大きく変わります。特に、ピン・PAP(Positive Axis Point)・CG(重心)の位置関係により、フレアリングの幅や位置が決まります。この配置が他のボールと違っていた場合、軌道上で指穴を通過する位置にフレアリングが来てしまうことがあります。
◆ 原因の可能性2:表面素材やRG値の違い
カバーストック(表面素材)が異なるボール、あるいはRG(回転半径)やディファレンシャル(フレアポテンシャル)の違いによっても、軌道やフレア位置が変化します。中には特に強いフレア特性を持つボールがあり、それが原因で他のボールと挙動が変わるケースも。
◆ 原因の可能性3:あなたの投げ方との相性
もしあなたのフォームやリリースが比較的一貫しているにも関わらず、特定の1球だけでこの現象が起きる場合は、「そのボールの設計と、あなたの投げ方の相性が悪い」と考えるのが妥当です。
✅ 解決策
プロショップでPAPを測定し、レイアウトを再確認する
指穴の位置に近すぎるフレアリングが出るなら、レイアウトを変更
必要に応じて、他のボールと同様の軌道特性を持つように新しいボールを作成
動画で自分の投球を撮影し、問題がボール固有かフォーム由来かを確認
2. 左手二刀流ボウラーの手の内側保持
二刀流(ツーハンド)ボウラーとしての技術を磨く上で、「手が外に開いてしまう」「リリースで手首が早く返ってしまう」という悩みは非常に多くの選手に共通する課題です。特に左利きの二刀流ボウラーは、自身のフォームの中で「手の内側を保つ」という技術をどう安定させるかが、回転軸の安定やリリースの一貫性に直結します。
◆ なぜ「手の内側を保つこと」が大事なのか?
「手の内側を保つ」というのは、ボールをリリースする瞬間に、手のひらがボールの背面から支えるような位置関係を保っている状態を指します。手が早く返ってしまったり、外側に逃げるような動きになると、回転が乱れたり、ボールが早めにブレイクしすぎるなどの問題が起こります。
特に二刀流ボウラーにおいては、リリースの際の手首の角度や肩の使い方が微妙に変化することで、リリースの安定感が大きく損なわれることがあります。逆に、常に「手が内側から支えている状態」を保てると、スピン量と回転軸をコントロールしやすくなり、ピンアクションも格段に良くなります。
◆ マーク・ベイカーの「胸板(ブレストプレート)理論」
マークはこの問題に対して非常にユニークで実用的なアプローチを提案しています。それが「胸板(ブレストプレート)の向きがすべてをコントロールする」という理論です。
胸板がダウンレーン(目標方向)を向いている状態を保つこと
→ これが肩の向きを安定させる
→ 肩の向きが安定すれば、手首や親指(※ツーハンドは入ってないが、リリース動作には関係)が暴れにくくなる
つまり、フォームの中で体幹(特に胸と肩)をいかにターゲットに正対させるかが、手の内側保持に直結するという考え方です。
◆ 実践ポイントと練習法
ミラー練習
練習場で鏡を使って、胸がどこを向いているかを意識的にチェック
リリースの瞬間も、胸が斜めにならず正面に向いていることを確認
スローアプローチ練習
通常より半分のスピードでアプローチし、胸の角度を意識しながらスイングする
体の回転と手首の動きがどのように連動しているかを体感
映像フィードバック
自分の投球動画を撮って、リリース時の肩と胸の向きを確認
リリース前に体が「早く開いてしまっていないか」を確認することで修正点が見える
◆ よくあるミスと修正のヒント
肩が先に開くと、手が外に流れる
→ 特にリリース直前に体幹を回しすぎないようにする
手首が早く返る
→ 手首ではなく、体全体で投げる意識を持つことで軽減
3. プッシュアウェイの有無とスイングの関係
「プッシュアウェイ(Push Away)」とは、アプローチの初期段階でボールを前方に出す動作のことを指します。これは伝統的な片手投げスタイルでは一般的な動作ですが、最近は特にジュニア世代の二刀流ボウラー(ツーハンド)において、プッシュアウェイをまったく行わず、いきなりスイングを始めるスタイルも増えてきています。
この項目では、プッシュアウェイの有無がスイングに与える影響や、その重要性について詳しく解説していきます。
◆ プッシュアウェイとは何か?
プッシュアウェイは、アプローチの最初のステップまたは二歩目に合わせて、ボールを身体の前に軽く「押し出す」動作です。これは、スイングを自然に、かつリズムよく始めるための準備動作であり、ボールの重みと身体の動きを同調させるタイミングの要です。
この動作があることにより、以下のようなメリットがあります:
スイングの始動タイミングが安定する
ボールの重力を利用して自然な振り子運動が生まれる
身体とスイングの動きが一体化しやすくなる
◆ 二刀流スタイルにおけるプッシュアウェイの変化
近年、特にジュニアや若年層のボウラーを中心に、「プッシュアウェイをしない二刀流スタイル」が目立つようになりました。これは、ボールを手元で保持したまま、スイングを直接後方にスタートさせる動作で、見た目には非常にスピーディーかつコンパクトに見えます。
一見合理的に見えるこのスタイルですが、マーク・ベイカーは「プッシュアウェイがないとスイングが始まらない」と強く主張しています。彼はこの現象を「ブランコ理論(Swing Set Analogy)」で説明しています。
◆ ブランコ理論とは?
マーク・ベイカーは、プッシュアウェイの重要性を「ブランコを漕ぐ動作」に例えています。
「子どもをブランコに乗せたら、最初に前に押してあげるよね?それがないとブランコは動かない。ボウリングのスイングも同じだよ。」
つまり、プッシュアウェイはスイングの“初速”を与える役割を担っており、これがないと自然なスイングのリズムが生まれにくくなるというわけです。
◆ 実例:ジェイソン・ベルモンテのスタイル
マークは、世界最強の二刀流ボウラー、ジェイソン・ベルモンテ(Jason Belmonte)を例に挙げています。彼はプッシュアウェイをしっかり行っており、その動作は1970年代のクラシックなスタイルに近いとのこと。
彼のプッシュアウェイは、コンパクトながらもしっかりとボールを前に出すことで、スイングに自然な流れを生み、リズムとタイミングを作り出しています。このように、トッププロでもプッシュアウェイを活用しているのは、「スイングの構築において不可欠だから」です。
◆ プッシュアウェイを導入する練習法
鏡を使ってフォーム確認
スタートポジションでボールを前に出す動作をスローモーションで確認
背筋を伸ばし、自然な振り子を意識
テンポ練習(1・2・3)
「1:スタート」「2:プッシュ」「3:スイング」とリズムを刻んで投球
音楽のリズムに合わせて投げるとタイミングが取りやすい
片手でのスイング練習(ツーハンドでも有効)
支え手を使わず、プッシュアウェイからスイングへ流れる動作を確認
体幹とバランス感覚を養う
4. ブレイクポイントの調整
ボウリングにおける「ブレイクポイント(Break Point)」とは、ボールがオイルゾーンを抜けてフックし始める転換点のことです。スコアを安定させる上で、このポイントを「いつ・どこに設定するか」が非常に重要です。
初心者や中級者の中には、「ボールがどこで曲がるかわからない」「ブレイクポイントが毎回ズレる」という悩みを持っている方も多いはず。ここでは、マーク・ベイカーが提唱するブレイクポイントの考え方と、その調整法について詳しく解説します。
◆ ブレイクポイントはどこにあるべきか?
マーク・ベイカーは、ブレイクポイントを「レーン上で最も大事なスポット」と位置付けています。彼の理論では、理想的なブレイクポイントは以下の条件を満たすべきだとしています。
距離的にはレーンの42〜46フィート地点
横位置としては、6〜8枚目(ボード)あたり
この位置からピンに対して“6度”の入射角を作れるようにする
この“6度”という数字は、アメリカUSBC(全米ボウリング協会)が「最もストライクが出やすい」と認定した入射角です。つまり、単に「曲がる場所」を探すのではなく、「最も効率よくストライクにつながる場所」を計算して見つける必要があるということです。
◆ なぜ毎回変えるべきではないのか?
他のコーチやボウラーの中には、「立ち位置が1枚右に動けば、ブレイクポイントも1枚右に」というような考えを持つ人もいます。いわゆる「1・1の法則」です。
しかし、マークはこれを否定し、「ブレイクポイントはなるべく一定にすべき」と主張しています。その理由は明快です。
「ピンの位置は固定されている。だからブレイクポイントも固定でなければならない。」
ピンは常に同じ場所にあるので、ブレイクポイントを大きく動かしてしまうと、入射角が変わってしまい、ストライクの確率が下がるというわけです。マークは、ブレイクポイントを固定し、そこに向かうラインを変えるという考え方を基本にしています。
◆ プレイラインによる違い
ただし、例外もあります。たとえば、レーンの外側(ファーストアロー付近)から投球する場合、ブレイクポイントは早め(38〜40フィート)になることがあります。逆に、内側(サード〜フィフスアロー)を攻める場合は、より遅いブレイクポイント(45〜47フィート)になることもあります。
この調整は「攻める角度」と「ボールの種類(表面素材・RG・ディファレンシャル)」によって微調整が必要です。
◆ 実践方法:ブレイクポイントの見つけ方
レーン上の観察
レーンの光の反射やオイルの残り具合を見て、オイルが切れる位置を目視で確認
ターゲットスポットの活用
レーンにあるドットやアローのマーカーを使って、自分の狙いと結果を記録する
一定のブレイクポイントを基準にラインを作る
たとえば「44フィート・7枚目」に決めたら、そこを通るように立ち位置や目線を調整
ボールトラッキングツールの活用
SPECTOやトラックITなどのデータ分析機器で実際の軌道を確認すると、より精度が高まります
◆ よくあるミスとその修正
毎フレームごとにラインを大きく変える
→ 原因がわからなくなるので、一定のブレイクポイントを基準に考える習慣を
ブレイクポイントが早すぎて手前で曲がる
→ オイルの量やボールの表面仕上げを見直す
ブレイクポイントが遅すぎてバックエンドで滑る
→ ボールの回転数やスピードの調整を検討
5. ボールスピードの向上
ボールスピードは、回転数と並んでボウリングにおける「武器」になります。スピードが速いほどピンヒットのエネルギーが高まり、ミスしてもピンが倒れる可能性が上がるという利点があります。しかし、ただ力任せに速く投げればいいというわけではなく、フォームや体の使い方に大きく左右される技術要素です。
マーク・ベイカーは「ボールスピードは主に3つの要素で決まる」と説明しています。
◆ スピードを決定づける3要素
体格・体重(体の質量)
スイングの長さ
足の速さ(アプローチ時のステップスピード)
この3つを組み合わせて考えることで、自分に合ったスピードアップの方法が見えてきます。
◆ 1. 体格と体の使い方
体が大きい、筋肉量が多い人は、自然と力が加わりやすいため、基本的にスピードが出やすい傾向にあります。しかし、逆に体が小柄な方や女性のボウラーは、筋力だけでスピードを出すのは難しいため、「体の使い方」を工夫する必要があります。
ポイントは、下半身主導でスイングを引き出すこと。腕だけでボールを振るのではなく、歩幅やスライドステップを強調し、「体全体の動きの流れにボールを乗せる」ようにしましょう。
◆ 2. スイングの長さとテンポ
スイングが短いと、それだけ加速距離が短くなります。スイングが長ければ、振り子運動による遠心力が生まれ、ボールに自然なスピードが乗ります。ここで注意したいのは、「手で引っ張って長くする」のではなく、「自然に後ろに下がる振り子」を意識することです。
おすすめは、背中の後ろまでボールが振れるスイングフォームを意識する練習。背骨に沿ってボールが落ちていくようなイメージを持つことで、余計な力を使わずにスピードを得ることができます。
◆ 3. 足の速さ=スピードの加速エンジン
実は、ボールスピードを向上させるうえで、足のスピードこそが最も重要な要素です。
マークは「スピードが欲しいなら、足を速く動かせ」と繰り返し指導しています。アプローチの最後の2歩、特にスライド前のステップ(通称:パワーステップ)が力強く、速くなれば、そのエネルギーがボールに伝わります。
練習では、次のような方法を試してみましょう:
通常より速いテンポでのステップ練習
後半2歩を「1・2」のリズムで素早く行う
最後のスライドでしっかりブレーキをかけて、力を下方向へ伝える
◆ よくある間違いとその改善
| よくあるミス | 改善ポイント |
|---|---|
| 肩の力でボールを速く投げようとする | → 腕ではなく足のスピードとスイングを意識 |
| スイングを無理に速く振る | → 自然な振り子で遠心力を活用する |
| スライドで勢いが止まる | → スライド前の加速ステップに集中 |
◆ 練習メニュー例
テンポスイング練習(無投球)
5歩目まで素早く歩き、振り子スイングの速度を確認
軽いボールでのスイング練習
10ポンド以下のボールでフォームとスイングの長さを確認
ミディアムテンポ投球
通常の半テンポ速く投球し、スピード感を体に覚えさせる
6. スランプからの脱出法
ボウリングを続けていれば、どんなレベルのボウラーでも必ずぶつかる壁——それが「スランプ」です。ストライクが出ない、スペアが取れない、投げても投げても手応えがない…。スランプに陥ったとき、どうすれば再び調子を取り戻せるのでしょうか?
マーク・ベイカーは「スランプから抜け出すには、技術的なことよりも“心構え”を変えることが最も重要だ」と言います。以下では、彼の考え方をもとに、スランプ脱出のための具体的な方法を解説します。
◆ スランプの本質とは?
まず、スランプとは単に「ストライクが出ない」「スコアが伸びない」という状態だけを指すのではありません。マークは、スランプをこう定義しています:
「思い通りに投げているつもりでも、結果が伴わず、自信が持てなくなっている状態」
つまり、技術的な問題よりも“メンタル”が原因で調子が悪くなっているケースが多いということです。
◆ スランプ脱出の第一歩:「期待値を下げる」
マークが最も強調するのがこのポイント。
「200点を目指すのではなく、まず“9本倒す”ことを目標にするべきだ」
スコアやストライクばかりを意識すると、うまくいかないときにストレスがたまり、それが投球に悪影響を及ぼします。そこで、まずは“ヒット(ポケット)に入れる”ことだけに集中し、「ストライクでなくてもいいから、ポケットを安定して狙える状態を作る」ことを最優先にします。
この戦略は、実際のスコアには現れなくても、心の安定と自信の再構築に非常に効果的です。
◆ 「9本+スペア」で得られるポジティブフィードバック
「9本倒す→スペアを取る」という動作を繰り返すことで、ゲーム中に「できた」という感覚が増え、少しずつ自信が戻ってきます。人間の脳は成功体験を繰り返すことで前向きなモードに切り替わるため、スランプ時には意図的に成功体験を作ることが重要です。
「ポケットに入り続ければ、いずれストライクは戻ってくる。」
マークはこの言葉を繰り返し使っています。
◆ 実践メニュー:スランプ時の3ステップ練習法
「9本倒す」だけを目指したゲーム
スコアを記録せず、毎投「ポケットに入ったかどうか」だけを評価対象にする
ストライクが出ても「たまたま」くらいの感覚でOK
「スペア特化練習」
残ったピンの種類にかかわらず、どの角度からでも必ず取る意識
ミスしても「次の1本」に集中
「メンタルルーチンの確立」
毎投前に「深呼吸」「体のチェック」「目標確認」など、一定のルーチンを取り入れる
体と心をリセットする習慣を作ることで、集中力が安定
◆ よくある落とし穴と注意点
| 落とし穴 | 修正ポイント |
|---|---|
| スランプから抜けようとしてフォームを大幅に変える | → 原因不明のままフォームをいじると逆効果になる可能性あり。まずは“ポケット狙い”を徹底 |
| 他人のアドバイスを聞きすぎて迷走 | → 意見は聞いても、最終判断は自分で。自分の感覚を信じる勇気も必要 |
| スコアにこだわりすぎる | → “過程”を見つめることが、結果的にスコア改善に繋がる |
7. 焼けたレーンでの対応
「焼けたレーン(英語では“burnt lane”)」とは、ボウリングの試合や長時間のプレーによって、レーン上のオイルが乾いてしまい、ボールが過剰にフックしてしまう状態のことを指します。特に、表面素材の強いボールや高回転(ハイレブ)で投げる二刀流ボウラーにとっては、この“焼け”は非常にシビアな問題になります。
焼けたレーンで対応を誤ると、ボールが手前で暴れすぎてポケットに届かず、スプリットやガターに直結してしまいます。マーク・ベイカーは、特にツーハンドのボウラーがこの状況で成功するためには、「アグレッシブなライン変更」と「思い切った立ち位置の調整」が必須だと述べています。
◆ なぜ焼けたレーンが問題なのか?
レーン上のオイルは、ボールが通るたびに“少しずつ削られる”ように消耗していきます。このため、試合終盤や複数ゲームを投げた後は、同じラインを通していても、手前でボールが予想以上に曲がってしまい、コントロールが非常に難しくなります。
特に高回転の二刀流ボウラーは、そもそもボールの動きが強いため、焼けたレーンではすぐに限界が来る傾向があります。
◆ マーク・ベイカー流「焼けたレーン」の基本対処法
マークが推奨するのは、以下の3つの大きな調整です。
立ち位置を大胆に左へ
5枚以上左へ歩き、完全に新しいラインを使う
特に、5〜6番目のアロー(25〜30枚目)を通すことを想定する
視線(ターゲット)も大きく左へシフト
単に立ち位置を動かすだけでなく、ブレイクポイントも変える
目線を第4アロー(20枚目)から外へ出すことも
“第三のアロー”が第一のアローになる意識を持つ
マークのユニークな考え方として、「ツーハンドの人にとっては、第一アローが第三アローだ」と言う
つまり、レーンの左側でゲームを展開する感覚を持つ
◆ 実践ライン例(ツーハンド用)
| 状況 | 推奨ライン | ブレイクポイント | 備考 |
|---|---|---|---|
| 焼けたスポーツコンディション | スタンス:35枚目 | 45ft地点の7〜9枚目 | フィフスアロー通過も視野に |
| ハウスでの焼け状態 | スタンス:30枚目 | 43ft地点の10枚目前後 | 速い足+軌道の安定化が必要 |
◆ 投球で意識すべきポイント
しっかり左へ歩いて身体を開く(クロスオーバー)
歩幅を小さくしてでも身体をレーンの左側へ向けることで、ラインの見通しが良くなる
手前で“抜く”感覚を意識
焼けたレーンではスピンを抑え、手前の摩擦を最小限にする必要がある
ボールの回転を意識的にコントロールすることも重要
ボール選択の見直しも忘れずに
表面の粗いボール(サンド加工)は避け、ポリッシュ系または対称コアのボールを選ぶ
スキッド(滑り)が出やすいボールを選ぶと扱いやすい
◆ 練習で取り入れたいメニュー
“ゾーン5”からの投球練習
レーンを5等分したうちの「最も左のゾーン」を使って投げる
4・5アローを視覚的に狙う練習
普段の第2アローではなく、意図的に第4・5アローに目線を持っていく
投球テンポと回転数の調整
スピードを少し上げて、回転を抑える投球フォームを身につける
8. バックスイング時に腰を打つ問題
「投球中にボールが腰に当たってしまう」という悩みは、初級者から中級者のボウラーにとても多く見られる課題です。これが起きるとスイングが不安定になり、フォーム全体が崩れ、思ったようなラインやスピードが出せなくなります。
特に4歩助走を採用しているボウラーでこの問題が多く見られるのは、足の運び方(ステップ)とスイングパス(ボールの軌道)の関係が密接に影響しているからです。マーク・ベイカーはこの問題について非常に具体的に解説し、正しいステップの修正によって改善できると指導しています。
◆ 腰を打ってしまう主な原因とは?
マークによると、バックスイング時に腰を打つボウラーの多くは、「ステップの方向と配置」に問題があるとしています。
具体的には:
2歩目のステップが外側(身体の外側)に出てしまっている
その結果、3歩目(ピボットステップ)が右に押し出され、スイングのスペースが狭くなる
狭くなったスイングパスの中で、ボールが腰に当たる
特に4歩助走の場合は、ステップの数が少ない分、1歩1歩の正確性が非常に重要になります。たった1歩目の方向がズレただけで、全体のリズムとスイングパスに大きく影響が出るのです。
◆ マーク・ベイカーの「ステップ配置理論」
マークが推奨する解決法は、「2歩目をまっすぐ、あるいは頭の真下に向けて踏み込む」ことです。右投げの場合、次のようなステップの流れになります。
1歩目:通常の助走の始まり(まっすぐ)
2歩目:まっすぐ、またはやや左に踏み出す(クロスしすぎない)
3歩目(ピボットステップ):頭の真下または内側にステップ
4歩目(スライド):バランスよく前方へ滑り込む
このようにステップを調整すると、スイングパスに「自然な通り道」ができ、ボールが腰にぶつかることなく後方に引かれていくようになります。
◆ よくある誤解:「もっとクロスさせれば避けられる?」
多くのボウラーが、「2歩目を大きくクロスオーバーすれば、ボールが身体の右側に来るのを防げる」と誤解しています。しかしこれは逆効果です。
大きなクロスステップを取ると、3歩目が身体の外に押し出されてしまい、ボールの通り道が“腰のライン”に入り込んでしまいます。結果として、スイング時に腰に当たる確率が高まるのです。
マークは、「クロスは必要だが、あくまで“軽め”にとどめ、2歩目と3歩目は自分の頭の下(中心線)に配置すること」が最も重要だと繰り返し強調しています。
◆ 実践的な修正法:ステップ練習
ミラー練習でステップの角度をチェック
鏡を使って、ステップごとに足の出し方を確認
2歩目が外に流れていないか、3歩目が右にズレていないかをチェック
ステップ+スイング分離練習
実際に投球せず、ステップとスイングの連動を繰り返し練習
ボールを持たずにリズムと空間を感じるトレーニング
低速での反復練習(スローステップ法)
ゆっくりとした動作でステップを確認し、無意識に正しいルートを体に覚えさせる
◆ スイング軌道の補足ポイント
背骨に沿った振り子スイングを意識
ボールが体から離れないよう、スイング中は「肩から垂らすように」動かす
肘を身体の近くに保つ
スイングの“横ぶれ”を抑え、直線的な動きに近づける
9. 近いターゲットを見ることの影響
ボウリングにおける「ターゲットの見方」は、意外にもスコアを大きく左右する重要な要素です。多くのプレイヤーが、ドット(足元のマーク)、アロー(15フィート先の矢印)、スパー(30フィート付近の目標点)など、異なる位置を目線のターゲットとして選んでいます。
その中でも、「近いターゲット——特にドット付近を見て投げる」ことが良いか悪いかについては意見が分かれます。マーク・ベイカーはこのテーマに対し、「近くを見すぎることがフォームに悪影響を及ぼす可能性がある」とし、その理由を科学的かつ実践的に説明しています。
◆ 「近いターゲット」とはどこか?
一般的なターゲットポイントには以下の3つがあります:
| ターゲット位置 | 距離(ファウルラインから) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| ドット | 約3〜6フィート(1〜2m) | 足元のマーク。初心者に多い |
| アロー | 約15フィート(4.5m) | 伝統的な目安。多くの中〜上級者が使用 |
| スパー/ダウンレーン | 約35〜45フィート(10m前後) | プロや戦略的プレイヤー向け。遠くを見る |
マークの主張は明確です——「ドットを見ることは、頭の傾きと体の姿勢に悪影響を与える可能性がある」というものです。
◆ 頭を下げすぎることによる弊害
ターゲットが近すぎると、目線を下げる必要があります。これによって自然と頭が前方へ傾き、姿勢が崩れるのです。姿勢の崩れは、以下のような影響をもたらします:
肩が下がりすぎて、スイングの軌道が外れる
バランスが崩れ、リリースのタイミングが不安定になる
肩主導の“投げ”になってしまい、スムーズな振り子運動が失われる
特に身長が高いボウラー(180cm以上)では、目線を下に落とすことで頭の傾斜が大きくなり、フォームへの影響が顕著に現れます。
マークは自身が6フィート4インチ(約193cm)という高身長であることを挙げ、「目線を下げると、自分の頭が大きく前に出て、投球に悪影響が出る」と語っています。
◆ 正しい目線の設定方法
理想的な目線のターゲットは「アロー付近」または「アローの少し先」に設定するのが一般的です。これにより、以下のメリットがあります:
姿勢を正しく保てる(頭が下がらない)
投球中も目線が安定しやすい
スイングに余裕が生まれ、フォーム全体が自然になる
ダウンレーンのオイル変化も見極めやすい
特に上級者や競技志向のプレイヤーには、35〜45フィート先の「ブレイクポイント」を見る意識が推奨されます。これにより、レーン変化への対応力が大きく向上します。
◆ 例外:近くを見ても成功しているプレイヤー
とはいえ、「近くを見て成功しているプロ」もいます。たとえば:
リズ・ジョンソン(Liz Johnson):ファウルラインを見るスタイルで長年女子プロをリード
ウェス・マロット(Wes Malott):PBAの実力者で、同様に非常に近い目線を使う
これらの選手は「近くを見ても頭の姿勢を崩さない」高い身体能力と再現性を持っているため、それが可能なのです。しかし、マークは次のように言います:
「私はそれができないから、教えることもできない。自分が信じる形でしか教えられない。」
つまり、すべてのボウラーが「近くを見る」スタイルで成功できるわけではないということです。
◆ 練習法:目線の最適化トレーニング
姿勢チェック練習
鏡や動画で、自分の投球中の頭の位置をチェック
目線をどこに置いた時に最もフォームが安定するか確認
遠くを見てのアプローチ練習
あえてスパー(30フィート以上)を目標にして投げることで、フォームのバランスを保つ練習に
視線固定ドリル
ターゲットに視線を固定したまま、1歩投げでフォームを確認
頭の位置をキープする感覚を身体に覚えさせる
10. 左足の角度と安定した着地
ボウリングの投球において「スライド足」(右投げの場合は左足)の使い方は、フォームの安定性、バランス、リリースの質、さらにはケガの予防にも大きな影響を与える非常に重要な要素です。中でも、「左足の角度」は、安定した着地と正確なリリースを導く鍵になります。
マーク・ベイカーは、「左足がどう向いているかで、胸と腰の開き、さらには投球の方向性までもが変わる」と語ります。ここでは、左足の角度をどのように調整すべきか、そしてそれが着地とパフォーマンスにどう影響するかを詳しく見ていきましょう。
◆ 左足の角度が影響を及ぼす3つの要素
体の開き具合(胸・腰・肩の向き)
スライドの安定性
リリース方向の制御
ボウラーがアプローチの最後でスライドしながら投球する際、左足の角度によって、体の「開き具合」が変わります。体が開きすぎると外ミス(ボールが右に外れる)、閉じすぎると内ミス(左に引っ張る)につながります。
◆ 左足の理想的な角度とは?
マークの指導では、左足のつま先は「正面を向いていても良いし、10〜20度ほど開いていても良い」とされています。ただし、それはあくまでレーンのどの位置を攻めるかによって変えるべきだというのがポイントです。
外側のライン(1〜2アロー)を攻める場合
左足は比較的「まっすぐ」でもOK
体を閉じた状態でリリースできるため、角度をつけすぎると逆効果
中〜内側のライン(3〜5アロー)を攻める場合
左足を「10〜20度開く」ことで体の開きがスムーズになり、スイングパスに余裕が生まれる
特にレーンの左側を使うようになると、この角度調整が非常に有効
◆ 左足の角度と体の連動性
左足を開くことで、自然に腰と胸がターゲット方向に向きやすくなります。これは特に、投球の際に「体を閉じすぎて手が出にくくなる」タイプのボウラーにとって非常に有効です。
一方で、昔のスタイルでは「左足を内側に絞って、かかとを上げるような形」が一般的でしたが、マークはこれを否定しています。
「左足を内にねじると、左のヒップが引っ込んでしまい、体の回転が不自然になる。」
その結果、リリース時に肩や腕がブロックされ、回転の掛かり方やラインが狂ってしまうリスクが高まるのです。
◆ 安定した着地を得るためのフォームポイント
膝を柔らかく曲げる
着地時に膝が硬いと、衝撃でバランスを崩しやすい
膝をしなやかに使うことで、体全体のブレが減る
かかとから着地する意識
左足のスライドは、つま先ではなく「かかと」から滑り始めるのが理想
これにより体重が安定し、前傾姿勢を保ちやすくなる
左腕でバランスを取る
リリース時に左腕を「横」または「下」に保つことで、体の回転を抑え、着地が安定する
◆ 練習法:左足の角度と着地安定性を高めるためのメニュー
スタンス確認練習
鏡や動画を使って、左足の角度と胸の向きをセットでチェック
ワンステップ・スライド練習
一歩だけ踏み出して左足でスライド、姿勢とバランスの確認
左足のつま先がどこを向いているかを意識
角度別スライド実験
左足の角度を0度・10度・20度と変えて、それぞれの着地の安定性を体感
最もフィーリングが良く、スムーズに振れる角度を見つける
11. マーク・ベイカーとのセッション方法
マーク・ベイカー(Mark Baker)は、PBA(プロボウラーズ・アソシエーション)の元トッププロであり、現在はアメリカを代表するボウリングコーチの一人として世界中のボウラーを指導しています。彼の指導は「身体の機能に基づく理論」と「感覚に頼らない再現性のある技術」が融合しており、数多くのPBA選手から一般ボウラーまで、あらゆるレベルのプレイヤーが彼のもとで技術を磨いています。
ここでは、そんなマーク・ベイカーとのセッション(レッスン)を受けたい場合、どのようにコンタクトを取り、どんな内容が期待できるのかを詳しくご紹介します。
◆ セッションを受ける方法
マークとのセッションを希望する場合は、まず彼の公式ウェブサイトにアクセスしましょう:
📌 Mark Baker Bowling(https://www.markbakerbowling.com)
このサイト内には以下の情報が掲載されています:
セッションの申し込み方法
レッスン料金の目安
動画教材の購入ページ
トレーニングセンターの場所とスケジュール
マークは動画でも語っている通り、現在は世界各地から受講希望者が訪れており、アメリカ国内はもちろん、イギリス、スコットランド、オーストラリア、日本など、グローバルな人気を誇っています。そのため、スケジュールにはある程度の余裕を持って問い合わせするのがオススメです。
◆ 問い合わせの流れ(例)
ウェブサイトの「Contact」ページからメールを送信
自己紹介(名前、出身地、ボウリング歴、アベレージなど)
どのような内容のセッションを希望するか(例:フォームの改善、回転数アップ、ライン取りなど)
希望する時期や曜日
マーク本人またはスタッフから返信が来る
スケジュール調整の提案
レッスンの所要時間や費用の説明
予約完了後、現地またはリモートでセッション実施
アメリカ・カリフォルニアのベイカー・ボウリング・トレーニングセンターが主な拠点
◆ レッスンの形式と内容
マーク・ベイカーのセッションは、受講者のスキルレベルや目的に応じてカスタマイズされます。代表的な内容は以下のとおり:
フォームの構造的分析
動画を撮影してフォームを分解、改善ポイントを明確に説明
姿勢、ステップ、スイング、リリースを段階的に指導
スイングと足のタイミング調整
特に重要とされる「タイミングスポット」の理解と実践
“足がボールを先導する”投球を体得するための練習
メンタルトレーニング
試合中の考え方、失投後の立て直し方
自分の性格に合わせた戦略づくり
オイルパターンへの対応法
レーンコンディションの読み方と適応練習
焼けたレーンやスポーツコンディションへの対応策
◆ オンラインセッションも可能?
パンデミック以降、マークはオンライン形式のレッスンやアドバイスにも対応を始めています。主に次のような方法で受講可能:
フォーム動画を送付し、メールやZoomでフィードバックを受ける
オンラインでのコンサルティング(技術+メンタル戦略)
これにより、アメリカ国外に住むボウラーでも、距離の壁を越えてマークからのアドバイスを受けることが可能になりました。
◆ 料金と所要時間の目安(※変動あり)
対面レッスン(60分〜90分):$150〜$250程度
オンライン診断+フィードバック:$75〜$150程度
グループセッション(複数名):1人あたり割安料金あり
価格は為替や地域、時期によって変動するため、必ず事前に確認しましょう。
◆ 人気ゆえの注意点
マークは現在、毎月多数のセッションをこなしており、特にジュニアゴールド大会シーズン(7月)やPBA関連の期間はスケジュールが埋まりやすくなっています。セッションを希望する場合は1〜2ヶ月前には問い合わせることをおすすめします。
12. 二刀流ボウラーのバックスイング
現代のボウリング界において、二刀流(ツーハンド)スタイルはすでに一つの確立された戦術的な投球法となっています。その中でも、バックスイングの取り方は、ボールの軌道、回転量、タイミング、そしてスムーズなリリースに大きく影響する極めて重要な要素です。
ツーハンドボウラーにとっては、ボールを両手で保持する関係上、片手のスイングよりも構造が異なり、「腕をまっすぐ伸ばすべきか」「少し曲げた方がいいのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
マーク・ベイカーはこのテーマに対して、「どちらが正しいという答えはまだ出ていないが、自分のタイミングスポットに近づけるフォームこそが正解だ」と語っています。
◆ バックスイングとは何を指すのか?(ツーハンド編)
ツーハンドボウラーにとってのバックスイングとは、以下の2つのパートに分かれます:
両手でボールを持った状態から、サポート手(非利き手)を外すまでの動作
サポートが外れた後、ボールが背中側に振り上がる“バックモーション”
この過程で「ボールの角度」や「腕の伸ばし方」が、フォーム全体のバランスやリズムに密接に関係してきます。
◆ 「腕をまっすぐ伸ばす」vs「少し曲げる」
このテーマは、二刀流の世界でも意見が分かれるところです。
| スタイル | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| まっすぐスイング | 腕を伸ばして大きく後ろへ | 軌道が安定しやすく、スピンが強い | 肩・背中に負担がかかることも |
| 曲げたスイング | 肘を軽く曲げてコンパクトに | 素早いタイミングが取りやすい | スイングが浅くなる可能性 |
マークはこれらの違いを、「どちらが“良い”ではなく、“あなたのタイミングスポットに近づけるか”がすべて」と強調します。
◆ タイミングスポットとは?
マークがたびたび使う「タイミングスポット」という言葉は、以下の条件が揃う瞬間のことを指します:
スライド足(左足)が完全に着地する瞬間
同時に、スイングが地面と平行に位置する
腕とボールが“リリース直前の準備状態”にある
この「左足のスライド」と「スイングの位置」が同時に揃った瞬間が、最もエネルギー効率が良く、正確なリリースが可能なタイミングです。
◆ 実際のプロ選手の例
ジェイソン・ベルモンテ:スイングはやや曲げ気味。タイミングに合わせてスムーズにスイングを構築
アンソニー・シモンセン:スイングは比較的コンパクトで、肘が柔軟に動いている
カイル・トループ:より大きなフリースイングに近く、腕が比較的まっすぐ伸びているタイプ
これらからも分かる通り、ツーハンドのトップ選手でもバックスイングに“正解”はなく、「自分に合ったスイングを見つけること」が最も重要です。
◆ 練習法:バックスイングを最適化する
スロー投球でスイング感覚を掴む
通常の半分程度のスピードで助走し、スイング中の腕の動きを確認
まっすぐと曲げたスイングの両方を試す
ミラー練習で背中側をチェック
バックスイング時に鏡を使い、肘や肩の高さ、腕の角度を確認
ボールが体のどこを通っているかを可視化
タイミングスポット練習
スライド足とスイングが重なる瞬間を意識し、その動作だけを繰り返すドリル
◆ よくある問題とその解決法
| 問題 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| バックスイングで腕がブレる | 肘の固定が不十分 | スイング前に肘の方向を決めておく |
| 背中に振りきれない | 腰や背中の柔軟性不足 | ストレッチ+小さめのボールで練習 |
| タイミングが毎回ずれる | スイングの一貫性不足 | 一歩投球やスローアプローチ練習でリズムを固定 |
13. バランスアームの位置
ボウリングのスイングやリリースにおいて「非投球側の腕」、つまりバランスアーム(Balance Arm)の使い方は、意外と見落とされがちな要素です。しかし、実はこのバランスアームの動き次第で、スイングの軌道や体の安定性、さらにはリリース時の正確さにまで大きな影響を与えます。
マーク・ベイカーはこの点について非常に詳細に言及し、「バランスアームが上がりすぎると重心が不安定になり、リリースが崩れる」と警告しています。ここでは、バランスアームの正しい位置と動かし方を理解し、より安定したフォームを作るための理論と練習法を紹介します。
◆ バランスアームの役割とは?
バランスアームの主な目的はその名の通り、「体のバランスを保つこと」です。投球中、特にリリース時は体が一方(投球側)に傾こうとする力が働きます。バランスアームを適切に使うことで、次のような効果が得られます:
上体のブレを抑える
スイング軌道を安定させる
腰や肩の傾き過ぎを防ぐ
投球後のフィニッシュ姿勢を安定させる
◆ マーク・ベイカーの「バランスアームは“下”へ」理論
マークは特に強調しているのが、「バランスアームを上に上げてはいけない」という点です。その理由は以下の通りです:
重心が上がる
→ 身体が「浮いた」ような状態になり、スイングが安定しない。腰が浮く
→ リリース直前に腰が持ち上がってしまい、ボールに力がうまく伝わらない。手がボールの“上”に回りやすくなる
→ 本来、ボールの後ろから支えるべき手が上から被さるようなリリースになり、回転が狂う。
マークはこの状態を「トップに巻き込む(come over the top)」と表現し、ボールの軌道が安定しない典型的なミスだと述べています。
◆ 「紐トレ」:マークが勧める簡単な矯正法
マークが紹介するユニークな矯正法として、「ロッド・ロス式の紐トレーニング」があります。
方法:
投球練習時に、左手首と腰のベルトループを紐で軽く結びつける
これにより、バランスアームを物理的に「上に上げられない」ようにする
このシンプルな方法で、無意識にバランスアームが高く上がってしまう癖を防ぎ、体の重心を低く安定させることができます。
◆ 正しいバランスアームの位置とは?
理想的な位置は、「肩より下」「胸の横あたり」に保つこと。そこから少し前方に向けて伸びる形が、体のバランスを保ちつつ、リリース時の体幹を安定させるベストポジションです。
マークは「拳闘(ボクシング)で両手を同時に前に出すような動き」を否定し、「リリース時にバランスアームが前に出すぎるのは、パンチを両手で打つようなもので逆効果」だと断言しています。
◆ よくある間違いとその修正法
| 誤った動き | 結果 | 修正ポイント |
|---|---|---|
| バランスアームが真上に上がる | 重心が浮く・フォームがブレる | 腕を胸の横で止め、肩より上げない |
| リリースと同時に前へ伸びる | ボディターンが崩れ、左肩が開く | リリース後は体の横でバランスを取る |
| バランスアームを意識しすぎて力む | 投球のリズムが崩れる | 軽く“添える”感覚を意識する |
◆ 練習法:バランスアームの感覚を養う
片足バランス練習
フィニッシュポジションで静止し、バランスアームの位置を意識
ミラーや動画でチェックし、肩より上がっていないかを確認
スロー投球+バランスアーム確認
通常よりゆっくりと投球し、バランスアームがどのタイミングでどこにあるかを確認
バランスアーム“無使用”ドリル
あえてバランスアームを使わず投げてみて、どれだけ体が不安定になるか体感
その後バランスアームを正しく使うことで安定感の違いを実感する
14. 70:30のルールと脚の使い方
ボウリングにおいて、「どこに力を入れてボールを投げているか?」という問いに対して、多くのボウラーが答えるのは「腕」や「手首」でしょう。しかし、マーク・ベイカーはこの考えに異を唱え、「プロとアマチュアの決定的な違いは、脚(レッグ)を使って投げているかどうかだ」と強調します。
彼が提唱するのが「70:30のルール」です。これは力の配分を70%脚、30%腕・上半身に置くことで、正確かつ一貫した投球が可能になるという理論です。
◆ なぜ脚がそんなに重要なのか?
脚は、単なる移動手段ではなく、パワーを地面から伝える“エンジン”の役割を果たします。地面をしっかりと捉えたステップとスライド、そしてタイミング良くスイングを導くことで、ボールに“自然な力”が伝わります。
一方、腕や肩で投げることに依存すると、フォームが毎回ブレやすく、ボールの回転数や軌道にもバラつきが生まれてしまいます。
マークはこれを以下のように表現しています:
「肩で投げれば“投げる”になる。脚で投げれば“転がす”になる。」
◆ 70:30ルールの具体的な意味
| 配分 | 説明 |
|---|---|
| 70% 脚 | 助走、スライド、踏み込みによって生まれるエネルギーをスイングに伝える。パワー源。 |
| 30% 腕・手・肩 | スイングの軌道維持、リリースのタイミング調整。力でなく“導く役割”。 |
このバランスを保つことで、フォームが自然に安定し、無駄な力みも減り、疲労も少なくなるというメリットがあります。
◆ 実際のプロはどう使っている?
プロボウラーは、どんなに速く・力強く投げているように見えても、そのパワーのほとんどは「脚→腰→肩→腕」という連動によって生まれています。スイングは振り子運動に近く、力で引っ張るのではなく、身体の自然な流れの中で発生しています。
彼らのフォームをスローで見ると、次のような特徴があります:
脚が地面にしっかり着地し、ブレーキが効いている
スライドと同時にスイングがリリースに向かって一致している
上半身は“後からついてくる”感覚
◆ 70:30を実現するための練習法
スローテンポ・ステップ練習
ステップの一歩一歩を意識して、足の動きだけでスイングを動かす感覚を体得
特に4歩目(右投げなら左足のスライド)で“体重をしっかり乗せる”ことが重要
スイングノーハンドドリル
ボールを持たずにアプローチだけ行い、スイングの開始と同時にどこに力が入っているかを確認
脚に意識を集中させる
ワンステップスライドドリル
最後の1歩だけでスライドしながらボールをリリースする練習
脚が“止まりながら”力を生む感覚を体得
◆ よくある誤解と修正法
| 誤解 | 結果 | 修正のヒント |
|---|---|---|
| 肩で振ればスピードが出る | 力み・バラつき・フォームの乱れ | スイングは“導く”だけ。足で加速する |
| 脚を速く動かせばいい | タイミングが崩れる・スイングと不一致 | スイングと足が“同調”するテンポを探す |
| スライドはおまけ | フィニッシュ姿勢が不安定に | スライドが投球の“終着点”。軸を支える柱 |
◆ マークが言う「70:30」と「50:50」の違いとは?
マークは次のように語っています:
「脚と肩が50:50だと、それはスイングではなく“スロー(投げ)”だ。スイングが正しく機能しているときは、70%が脚からくる。」
つまり、50:50は力任せな投球。70:30こそが、再現性のあるプロレベルのスイングなのです。
15. 筋力に頼らないスイング
「ボウリングは力のスポーツだ」と思われがちですが、実際には筋力に頼らない“しなやかなスイング”こそが、正確で一貫性のある投球につながるのです。
マーク・ベイカーは、多くのボウラーが無意識に「腕で投げよう」としてしまっている点に警鐘を鳴らしています。特に調子が悪いときや力んでいるとき、知らず知らずのうちに「筋力=パワー」と勘違いし、余計に力が入ってしまうのです。
ここでは、筋力に頼らず自然でスムーズなスイングを実現するための考え方と具体的な練習法を詳しく解説していきます。
◆ なぜ「筋力に頼るスイング」が問題なのか?
筋力を使ったスイングには、以下のような弊害があります:
スイング軌道が乱れる
力で振ろうとすると腕が外に開いたり、軌道が上下にブレたりして精度が落ちる
リリースタイミングがバラつく
腕の力でタイミングを合わせようとすると、ボールの落下ポイントが毎回変わってしまう
回転が安定しない
手首や指先が過剰に力むと、回転数・軸・入射角すべてに悪影響
疲労とケガの原因になる
特に肩、肘、手首にかかる負担が大きく、長時間の投球に向かなくなる
◆ 「しなやかなスイング」の理想形とは?
マーク・ベイカーは、筋力に頼らないスイングを「振り子運動(Pendulum Swing)」と表現します。つまり、重力に任せてボールを自然に振らせることを基本とします。
腕は力を入れず、ただ“ぶら下がっているだけ”
肩を起点に、自然に前後に振れるような軌道
重さと重力の流れに逆らわないリズム
このスイングを実現するには、「腕で持ち上げない」「肩で振らない」「手で押し出さない」という3つの“しない動作”を守ることが大切です。
◆ グリッププレッシャーの見直し
スイングの力みの多くは、「ボールの握り方(グリップ)」に起因します。マークは「スイングを柔らかくするには、まずグリップを緩めろ」と強調します。
指先にボールが引っかかる程度の“軽い力”で持つ
投球中に“落としそうな感覚”を怖がらず受け入れる
指だけで支えるのではなく、手全体のホールド感を意識
プロはこの“限界まで軽いグリップ”をマスターすることで、スイングの自然さを保っています。
◆ フットワークとタイミングの見直し
しなやかなスイングを支えるのは、「正しい足のリズムとタイミング」です。力で投げようとする人は、足がスイングに追いついておらず、腕だけが先に動いてしまいます。
正しいスイングは:
足のリズムが一定で
スイングの“戻り”とリリースが、スライドと一致
下半身がスイングを“導く”感覚
マークが繰り返し語る「タイミングスポット(スライドとスイングが平行になる瞬間)」を見つけることで、無理な力がいらなくなります。
◆ 筋力に頼らないスイングのための練習法
スイングオンリー練習(ノーステップ)
ボールを持ってその場でスイングだけを行い、力を入れずに振り子を作る
グリップ脱力ドリル
投球中に「握らずに指で引っかけるだけ」でどれだけリリースできるかを試す
スロースイングアプローチ
通常の半分のスピードでアプローチし、すべての動きを意識的に“脱力”
軽量ボールを使った連続スイング
10ポンド以下の軽いボールで10回連続でスイング、腕を使わずリズムだけで振る
◆ よくある間違いとその解決
| 問題 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| ボールが思ったより飛ばない | 力を抜きすぎてスピード不足 | 足の加速やスイングの長さで補う |
| リリースが不安定になる | グリップを弱めすぎ | “抜ける感覚”と“しっかり持つ”の中間を探す |
| 回転数が落ちる | 手を使わない意識が強すぎ | リリース時の“自然な手首の動き”は維持する |
16. ドリフトの修正
「ドリフト」とは、ボウリングの助走(アプローチ)中に、最初に立った位置と最後のスライド位置が横方向にズレてしまう現象を指します。多くのボウラーが無意識のうちに行っており、リリースの精度や投球ラインの再現性に大きな影響を及ぼす要素です。
マーク・ベイカーは、ドリフトを放置しておくと「リリース時のアングルが毎回変わってしまい、ライン取りが不安定になる」と警告しています。ここでは、ドリフトの原因から修正方法まで、実践的かつ詳しく解説していきます。
◆ ドリフトの種類とその影響
まず、ドリフトには大きく分けて2種類があります:
| ドリフトの方向 | 影響 |
|---|---|
| 右ドリフト(右投げ基準) | スイングが外側に逃げやすく、ターゲットを外す原因になる。特にタイトなラインでは致命的。 |
| 左ドリフト(右投げ基準) | インサイドから投げる際には許容されることもあるが、多すぎると体の開きが早くなりリリースが不安定に。 |
マーク・ベイカーは、特に5枚以上右にズレるドリフトを危険視しており、これが起きている場合は「すぐに修正すべきだ」と断言しています。
◆ なぜドリフトが起きるのか?
ドリフトの主な原因は、以下のような身体の動きにあります:
ステップの方向が一定でない
特に2歩目・3歩目(ピボットステップ)が外側に広がる
スイングパスが内側に入りすぎる
ボールが体に近すぎると、バランスを取ろうとして逆方向にズレる
目線と立ち位置のギャップが合っていない
立ち位置に対して視線が外を向いていると、自然と身体が“引き戻される”ように動く
投げ急ぎ・リズムの乱れ
助走が速すぎる、スライドが中途半端、リリースが合っていないなど、テンポのズレからドリフトが生まれる
◆ ドリフトの許容範囲
マークのガイドラインでは:
右ドリフト:3枚以内(理想は0〜2枚)
左ドリフト:最大7枚まで許容
特にプロレベルになると、「あえて3〜5枚左にドリフトする」戦略もありますが、それはあくまで意図的に行うものであり、無意識のドリフトは早急に修正すべきです。
◆ 修正方法①:ステップの再配置
マークは、「頭の真下に2歩目と3歩目を通す」ことを最優先に挙げています。
2歩目(右投げの場合:右足)を体の内側へ引き込むように踏み出す
3歩目(左足)も、頭の真下かやや内側に入れる
これにより、スイングパスと体重の軸が一致し、左右のバランスが整いやすくなります。
◆ 修正方法②:視線とアングルの一致
スタンス(立ち位置)と視線の差を「一定」に保つ
たとえば:
スタンス15枚目 → ターゲット10枚目(5枚差)
スタンス35枚目 → ターゲット21枚目(14枚差)
このように、「立ち位置が左に行くほど、ターゲットもそれに応じて外側に調整する」のが原則です。差が不自然だと、身体が勝手に修正しようとしてドリフトが発生します。
◆ 修正方法③:アプローチの確認練習
アプローチの“ラインテープ”練習
アプローチ上にマスキングテープでまっすぐな線を貼り、その上をまっすぐ歩く練習
最後のスライド位置でどれだけズレたかを視覚的に確認できる
ステップごとの停止練習
1歩ごとに意図的に止まり、どのステップでズレているかを確認する
ズレているステップだけを繰り返し練習
動画撮影によるフォームチェック
自分では気づけない動きのズレを映像で確認し、意識的に矯正する
◆ ドリフトの“戦略的活用”は上級者向け
プロレベルになると、あえてドリフトを使って体の向きを調整し、レーンの変化に対応する選手もいます。しかし、これは「ドリフトを意図的に制御できる」ことが前提。
初心者〜中級者が無意識にドリフトしてしまうのは、「身体のコントロールができていない証拠」です。まずはまっすぐ歩くことから始め、狙った位置に正確に立ち、正確にリリースできるフォームを目指しましょう。
17. 4歩から5歩へのアプローチ変更
「4歩助走から5歩助走に変えたいけれど、タイミングが合わずうまくいかない」――これは中級者以上の多くのボウラーが直面する技術的な壁です。マーク・ベイカーはこの問題に対し、「タイミングの再構築と“感覚のリセット”が必要」だと語ります。
一見シンプルに思える「歩数の追加」ですが、実際にはスイング、リズム、スタンス、プッシュアウェイのタイミングまで、フォームの根幹が変わる重大な調整です。ここでは、4歩から5歩への変更に伴う変化と、それをスムーズに実現するための方法を詳しく解説します。
◆ そもそも「歩数」はなぜ重要なのか?
ボウリングの助走における歩数は、スイングとの“タイミングの設計図”です。歩数が変われば、以下のような部分もすべて調整が必要になります:
ボールのプッシュアウェイタイミング
リリースとスライドの一致(タイミングスポット)
足の加速とスイングの長さのバランス
精神的なテンポ(ルーチン)
つまり、「歩数の違い=身体全体のリズムの違い」なのです。
◆ 4歩と5歩の違い:構造的な比較
| 要素 | 4歩助走 | 5歩助走 |
|---|---|---|
| 最初のステップ | プッシュアウェイと同時に始まる | 最初の1歩は“助走だけ”で、2歩目からプッシュアウェイ |
| リズム | 比較的タイト(短め) | 少し余裕があり、スイングのタイミングを取りやすい |
| 適性 | 正確さ・コンパクトさ重視 | パワー・タイミング重視 |
マークは「4歩から5歩に変えるのが難しいのは、“最初に踏み出す足”が変わるから」だと指摘します。右投げの場合、4歩では右足スタート、5歩では左足スタートになるため、“スタートのきっかけ”がそもそも変わってしまうのです。
◆ マーク・ベイカーの提案:「4歩 → 6歩」にする?
この問題に対してマークは非常にユニークな提案をしています。
「4歩から5歩がうまくいかないなら、いっそ“6歩”にしてみなさい。」
その意図はこうです:
6歩のうち、最初の2歩は“プレ歩行(助走だけ)”
3歩目から、従来の4歩のリズムをそのまま始める
つまり「今の投げ方を変えずに、アプローチに余裕を持たせる」発想
これによって、「足のスタートは変えず」「タイミングもそのまま」で、助走にリズムと安定性が加わります。特に体が大きい選手、テンポが速くなりがちな選手には効果的です。
◆ 実践練習法:歩数変更に慣れるために
“3歩スタート”リズム練習
「1・2(助走)→3(プッシュ)→4→5→6」で数えてリズムを体に覚えさせる
ノースイングステップ練習
ボールを持たずに、歩数だけでリズムを確認する
体の重心移動や足の幅、テンポが自然になるように意識
ビデオ比較でフォーム確認
4歩と5歩(または6歩)の動画を撮って比較
スイング開始とスライドのタイミングが一致しているかを確認
◆ 失敗しやすいポイントとその修正
| 問題 | 原因 | 修正のヒント |
|---|---|---|
| タイミングが合わない | プッシュアウェイが早すぎる | 2歩目でボールを前に出す意識を強める |
| リリースが早くなる | スライドとの一致が取れない | スライドのタイミングを1歩遅らせる |
| 最初の1歩でバランスを崩す | 歩幅が合っていない | 初歩を短く、リズムは一定に |
◆ 上級者向けアドバイス:5歩にするべきか?
歩数を増やすことが必ずしも“上級者向け”ではありません。大切なのは、「自分にとってどの歩数が一番リズムよく、正確に投げられるか」です。
マーク・ベイカーも「スタイルを変える必要があるのは、“理由があるとき”だけ」と言っています。たとえば:
ボールが重く感じる → 助走に余裕が欲しい
スイングが速くなりすぎる → タイミングを遅らせたい
リリースがぶれやすい → スライドとの一体感を高めたい
そんなときに、歩数変更は非常に有効です。
18. ターゲットラインへの歩行
「ターゲットラインへの歩行(Walking to the Target Line)」は、投球の安定性と精度に大きく関わる非常に重要な技術要素です。これは、助走中にどの方向へ歩いているかという動作に着目した考え方であり、ボウリングにおける「見えない基本」とも言えます。
マーク・ベイカーはこの点について、「ターゲットラインと足の進行方向が一致していないと、体がねじれ、リリースが不安定になる」と警告しています。多くのボウラーが無意識のうちにドリフトしたり、ターゲットとは別方向に歩いたりしており、これがリリースの乱れや精度の低下につながっているのです。
◆ そもそも「ターゲットラインへの歩行」とは?
これは単に「まっすぐ歩く」という意味ではなく、自分が狙っている投球ライン(ターゲットライン)に対して、身体全体が正しく向かい、歩行がそのライン上をトレースしているかどうかを指します。
ボウリングでは、以下の3点が一直線に揃うことが理想とされます:
スタンス(最初の立ち位置)
ターゲット(アローやスパーなど)
助走中の歩行(足の軌道)
◆ なぜターゲットラインに沿って歩く必要があるのか?
マーク・ベイカーは、「投球時に体の軸がねじれると、スイングパスが乱れ、回転・入射角・スピードに悪影響が出る」と説明します。特に次のような動きが、誤った歩行によって起こりやすくなります:
スイングが外側に逃げる
肩が開きすぎて引っ張る
体重移動がうまくいかず、リリースでブレる
ターゲットラインに対してまっすぐ歩けていれば、スイングパスも安定し、スムーズで一貫性のあるリリースが可能になります。
◆ マークの理論:「ラインに対して歩く」具体例
マークは、自身の経験と多くのプロの動きを分析した結果、「歩行は必ずしもレーンに対して平行でなくていい」と言います。むしろ、投げているラインに対して身体が自然に動くのが正解なのです。
たとえば:
| 投球ライン | スタンスの方向 | 歩行の意識 |
|---|---|---|
| ファーストアロー(外側) | やや内側寄り(10〜12枚目) | 少し左に歩く |
| サードアロー(内側) | 中央〜左寄り(20〜25枚目) | まっすぐまたは右に歩く |
| フィフスアロー(極端なインサイド) | 左端近く(30〜35枚目) | 右へ大きくドリフトしていく感覚 |
つまり、「右へ投げるライン」を投げているときは、自然と左へ歩くのが理にかなっています。これにより身体が開きすぎるのを防ぎ、リリースの方向性をキープできます。
◆ 実践練習法:ターゲットラインに沿って歩く
テープトレーニング
アプローチにマスキングテープを使って、自分のターゲットラインを視覚化
その上をなぞるように歩く練習を繰り返す
ターゲットウォーク法
自分が見ているアローの延長線上に意識を集中し、「そのライン上を歩く」イメージを強化
動画撮影で軌道チェック
上から、または正面から撮影し、足の動きと体のラインが一致しているかをチェック
◆ よくある間違いとその修正法
| ミス | 原因 | 修正方法 |
|---|---|---|
| ターゲットに向かっているのに外す | 足が別方向を向いている | 立ち位置と歩行をターゲットラインに揃える |
| 毎回着地位置が違う | 歩幅が不安定 | 足の幅とテンポを固定し、一定のリズムで歩く |
| 身体が開く | 歩き方がターゲットラインから外れている | 肩と腰をターゲット方向にロックし、胸でラインを“押す”意識 |
19. 頭と胸の安定
「どうしても投球時に頭が下がってしまう」「胸が折れてバランスが崩れる」——こうした悩みは、ボウリング中級者〜上級者に多く見られる非常に重要な課題です。見た目には些細なフォームのズレに思えるかもしれませんが、頭と胸の“安定”はスイング・リリース・回転・タイミングすべてに直結する根幹の要素です。
マーク・ベイカーは、このテーマについて非常に明確な立場を示しています。
「頭と胸が乱れるということは、スイングが安定しないということだ。スイングが安定しなければ、再現性も生まれない。」
ここでは、頭と胸の役割、よくあるエラーの原因、そして具体的な安定化の方法を実践的に解説していきます。
◆ なぜ「頭」と「胸」の安定が重要なのか?
ボウリングのスイングは、「体の中心軸」を基準にして振られる振り子運動です。そのため、頭と胸——つまり“体幹の上部”が不安定になると、スイングパス自体がズレてしまうのです。
特に二刀流(ツーハンド)ボウラーの場合、両手でボールを保持しているため、頭と胸の傾きがリリースに与える影響はより大きくなります。
◆ 頭の位置と投球精度の関係
マークは、「頭が早く落ちすぎる=肩が上がらず、スイングが小さくなる」と指摘します。これは以下のような動きにつながります:
リリースポイントが前にズレる
回転が浅くなる
タイミングが早くなって引っ張りミスが増える
逆に、頭がしっかりと軸の上に乗っていれば、スイングも自然と背中に抜け、リリースが体の近くで安定します。
◆ 胸(上体)の傾きは“段階的に”生まれるべき
マークは、頭と胸を「助走中はできるだけ高く、スイングが戻るタイミングで自然と下げるべき」だと教えています。
例えば:
助走1~3歩目 → 胸は高く、姿勢はほぼ直立
バックスイング開始時 → 軽く前傾し、視線をターゲット方向に合わせる
スライド〜リリース直前 → 肩と胸が前傾し、頭が自然と下がる
この“段階的な前傾”こそが、自然で再現性の高いフォームを作る鍵です。初めから前傾していると、肩の可動域が狭まり、回転やフォロースルーに支障をきたします。
◆ よくあるミスと修正ポイント
| ミス動作 | 原因 | 修正のための意識 |
|---|---|---|
| 頭が早く下がる | ターゲットが近すぎる(ドットを見るなど) | 目線をアローまたはダウンレーンに設定 |
| 胸が前に倒れる | 上体主導でリリースしている | 足とスイングが先行するタイミングに切り替える |
| スライド時に頭が左右に揺れる | 足元の安定感不足・軸のズレ | フィニッシュ姿勢で頭を“ボールの真上”に置く意識を持つ |
| 胸が折れて振り上げられない | 姿勢保持の筋力不足・リズムの乱れ | 上体の緊張を抜き、スイングに身を委ねるようなリリースを意識 |
◆ マークの具体的アドバイス:スイングを“下”に導く
マークは、頭や胸をコントロールするために「スイングを“高く”意識するよりも、“低く通す”意識の方がフォームが安定する」と説明します。
頭を高く保つ意識 → 姿勢は安定するが、肩が硬くなることもある
スイングを地面に沿って“低く”振る意識 → 自然と胸が落ち着き、重心も安定
◆ 練習法:頭と胸の安定感を養うドリル
鏡スイング練習
鏡の前でスイングを行い、頭の高さと傾きが一定かを確認
スローモーション投球
助走とスイングをスローテンポで行い、胸と頭がどう動いているかを体感
壁沿いシャドースイング
背中を壁につけた状態でスイングし、上体が前に倒れすぎないよう感覚を覚える
動画撮影による姿勢チェック
フィニッシュ時に頭がブレていないか、胸が折れていないかを確認する
20. オイルの変化への対応
ボウリングのスコアアップ、そしてコンスタントな実力発揮のために避けて通れないのが、オイルの変化(オイルブレイクダウン)への対応力です。
どんなに素晴らしいフォームやリリース技術を持っていても、レーンの変化に気づかずに同じラインを投げ続けてしまえば、ストライク率は一気に下がります。マーク・ベイカーはこの問題について、「対応の遅れが最大の敵」だと警告しています。
ここでは、オイルの変化とは何か、その兆候をどう見抜き、どう対応すべきかを実践的に解説します。
◆ オイルの変化とは?
ボウリングレーンには、ボールの摩擦と早期のフックを防ぐために、あらかじめオイルが塗布されています。ゲームが進むにつれ、以下のような変化が起きます:
ボールが通ったラインのオイルが削れていく
一部のゾーンにオイルが寄って滑りやすくなる(キャリー)
外側が乾いて、内側に油が残る状態になる(ブレイクダウン)
これにより、ボールのフックポイント(曲がり始めの位置)が早くなったり、逆に伸びたりして、思い通りのラインが通らなくなるのです。
◆ 変化を感じる“兆候”とは?
マーク・ベイカーは、変化を「感じる」感覚を養うことが最も重要だと説いています。その兆候には次のようなものがあります:
ポケットヒットしていたボールが急に高く入り始める(裏まで行く)
ストライクが出ていたのに、急に10番・7番などが残り始める
外ミスが戻らなくなり、内ミスが引っ張ってスプリットになる
これらは、オイルの変化を無視して同じラインを投げ続けているサインです。
◆ 対応の基本原則:「同じ場所を通し続けるな」
マークははっきりと言っています:
「オイルは変わる。だから、ボウラーも変われ。」
変化に対応するための基本的な戦略は以下の通りです:
立ち位置を移動する(1〜2枚左へ)
目線のターゲットも移動する(1〜2枚左へ)
ボールのスピードを調整する(早めにフックさせる/遅くして延ばす)
使用ボールを変える(表面素材、RG、コア特性の違い)
◆ マーク流・心理的対応法:「欲をかかない」
マークは「連続ストライク中にレーンが変化しても、“動くのが怖い”という気持ちは分かる」と語ります。しかし、次のようにアドバイスしています:
「フロント9を取ったら、俺なら次の1投は絶対に“1-1右に動いて強く投げる”」
これは、自分のアドレナリンやテンションが上がってスピードが出ることを見越した上での動きです。
つまり、自分の投球が変化していることも含めて、レーン変化と組み合わせて判断していく必要があります。
◆ オイル変化に強くなるための練習法
「移動しながらのスコア練習」
フレームごとに1枚ずつ立ち位置をずらし、どのラインが一番手応えがあるかを確認する
「スピード変化練習」
通常スピード、+1km/h、-1km/hと段階的に変化させて、どのようにフックポイントが変わるかを体感する
「ボールチェンジ練習」
同じ立ち位置で異なる表面仕上げ・コアのボールを投げ比べて、違いを理解する
◆ 上級者向けアドバイス:レーンを“読む”習慣
マークは、「レーンの状態を見ることも“投球”の一部」だと述べています。たとえば:
自分だけでなくペアの相手がどのラインを使っているかを見る
右利き/左利きの影響で、どのエリアが使われているかを意識する
ボールの軌道とピンアクションの変化を記録する
これらの情報が、次の一投での判断に直結します。
21. 長い待ち時間への対応
大会やリーグ戦、特に5人チームや混雑したコンディションでの試合では、「投球の合間の待ち時間」が長くなることがあります。普段の練習では数秒〜10秒で再投球するテンポに慣れているボウラーほど、この“待ち時間”が集中力や身体の感覚に悪影響を与えることがあります。
マーク・ベイカーはこのテーマに対し、「長時間の待機中も“競技の一部”として対応しなければならない」と明言します。以下では、精神面・身体面の両方から“待ち時間”への実践的な対応法を解説していきます。
◆ なぜ待ち時間が問題なのか?
体が冷える
筋肉が一度緩んでしまい、次のスイングに違和感が出る
集中力が切れる
外的要因(他人のプレー、音、話し声など)に気を取られる
メンタルの緊張が持続できない
“次の1投”に気持ちが乗らず、ミスしやすくなる
マークはこうした状況を「試合のリズムが壊れる瞬間」と位置づけ、ここで“自分のリズム”を保つことが、勝ち負けを左右するとしています。
◆ 身体面の対応:冷えを防ぐ・動き続ける
マークは、「ボウリング場でダッシュはできないが、じっとしている必要もない」と言います。
具体的には:
歩き続ける
投球の順番を待っている間、常にゆっくりと歩き回ることで血流を保つ
軽いストレッチ
手首、肩、股関節、足首などの可動部をゆるめることで、再投球時の滑らかさをキープ
シャドースイング
ボールを持たず、エアスイングをゆっくり数回行い、体の感覚をリセット
姿勢維持
座るとしても前傾姿勢を保ち、背筋を伸ばして呼吸を整える
◆ メンタル面の対応:集中を“引き伸ばす”方法
マークは「集中力を維持するのではなく、“再起動する”ことが重要」だと語ります。ずっと集中し続けるのは不可能。そこで、「次に投げるときに100%集中できる状態」を作るのがベストです。
実践的なメンタルテクニック:
投球前30秒ルーチン
投球順が近づいたら「呼吸→足チェック→目線→イメージ」のルーチンを実行
投球に集中するスイッチを“オン”にする
前のフレームを振り返る(短く)
「何が良かったか」「何を修正すべきか」を1フレーズで頭に思い浮かべる
イメージトレーニング
他のプレイヤーが投げている間に、自分の投球をイメージの中で再生する
“心のホームポジション”を作る
特定の言葉や動作(例:「よし、ここから」や、腰に手を当てるなど)で集中を呼び戻す習慣をつける
◆ 練習での再現も可能?
意外かもしれませんが、この“待ち時間対策”は練習時にも意識して取り組むことができます。
わざと3〜5分空けて投球する練習
フレーム間にストレッチや歩行を挟む
ペア練習やチーム練習で“順番待ち”を活かす意識を持つ
こうした「実戦に近い状況での練習」を取り入れることで、待機中の心身の保ち方が自然と身につきます。
◆ マークの実体験からのアドバイス
マーク・ベイカー自身は、PBAツアーに出場していた頃、2人ペア制でテンポよく投げるスタイルに慣れていたといいます。そのため、5人制や遅延の多い試合では集中力を保つのが難しかったとのこと。
彼の対策は「自分なりのテンポとルーチンを“どんな待ち時間でも守る”」ことでした。これは今でも生徒に対して最も強く伝えていることの一つです。
22. 左に外す原因
「ターゲットに向けて投げたつもりなのに、ボールが左に外れてしまう(右投げの場合)」——これは多くのボウラーが経験する、非常に一般的かつ悩ましい問題です。マーク・ベイカーはこの現象について、「見た目のズレではなく、“スライド位置とターゲットの角度”のミスマッチによって起こる」と明言しています。
一見単純に思える「左ミス」ですが、実はスイング、立ち位置、視線、ステップ軌道など、複数の要因が複雑に絡み合って起きているケースが多いのです。ここでは、その原因を深く掘り下げ、具体的な修正方法まで詳しく解説します。
◆ まず確認すべき「どの左ミスか?」
左に外すと一言で言っても、以下のようなタイプに分かれます:
| ミスタイプ | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 早く曲がる | フックが手前で強く出てしまい、ポケットを越えて裏側に行く | ターゲットの位置・角度ミス、スピード低下 |
| 引っ張る | リリースが早くなり、手前から左に出てしまう | 肩や上体の開き、リリースタイミングの乱れ |
| スイングが内に入る | スイングパスが内側にズレてターゲットを通過できない | スタンスやスライド位置のズレ |
◆ マーク・ベイカーの理論:「スライド位置とターゲットの関係」
マークが特に重視しているのは、「スライド位置とターゲットとの“差(ギャップ)”」です。
たとえば:
スライドが 15枚目
目線(ターゲット)が 10枚目
→ ギャップは 5枚
この関係性を保てば、スイングパスが自然と体の軸に沿って安定しやすくなります。
しかし、
スライド 18枚目
ターゲット 10枚目
→ ギャップが 8枚 に広がると、体の軸が過度に開き、リリース時に“巻き込む”動作が生まれやすくなります。これが左への引っ張りや、オーバーフックの主な原因です。
◆ よくある左ミスの具体的原因と修正ポイント
| 原因 | 解説 | 修正方法 |
|---|---|---|
| 肩が早く開いてしまう | 上体がターゲットより早く開いてスイングが内に巻き込まれる | 肩をリリース直前まで閉じる意識を持つ。左肩を“押さえる” |
| 視線が近すぎる | ドットや手前のアローを見ると、頭が下がりフォームが前に倒れる | アローより先(15〜20フィート)のダウンレーンを意識 |
| スイングパスが内側に入る | 肘や手首が体の前を通ってしまう | スイングは“背骨の横”を通す意識で、腕をぶら下げるように動かす |
| グリップが強すぎる | 指や手首に力が入り、ボールが早く回転してしまう | グリッププレッシャーを“限界まで軽く”設定し、柔らかく投げる |
| タイミングが早い | 足より先にスイングが来てしまい、力でリリースしてしまう | スライドとスイングのタイミングを合わせる(タイミングスポットを意識) |
◆ マークの推奨する“差のガイドライン”
スライドが 10枚目 → ターゲットは 5枚目(差=5枚)
スライドが 35枚目 → ターゲットは 21枚目(差=14枚)
このように、「スライド位置が左に行くほど、ターゲットも左に広がる」バランスを保つことがポイントです。
◆ 練習法:左ミスを修正する実践メニュー
スライドとターゲット差の記録練習
投球後に「どこに立って、どこを狙ったか」「結果はどうだったか」を毎投記録
感覚と結果のズレを可視化する
ミラー・シャドースイング
スイング中に肘が内に入りすぎていないかを確認
鏡を使って“腕が真下に降りているか”をチェック
肩ロック練習
プッシュアウェイ時に左肩を固定する意識を持つ
肩と骨盤が“ターゲットに対して開きすぎないように”意識
5投に1投“極端な外ミス”を投げる練習
敢えて右に大きく外す投球を行い、「いつもより内に巻き込んでいる」ことを体で理解
23. 一般的な高回転数とは?
ボウリングにおいて「回転数(Rev Rate)」は、ボールのパフォーマンスを左右する重要な数値です。ボールが1分間に何回転しているかを表すこの指標は、ピンへの衝撃力や角度(入射角)を決定づける要素であり、特にストライク率を高める上で非常に大きな影響を持ちます。
「自分の回転数は高いのか? 低いのか?」と疑問に思ったことのある方も多いのではないでしょうか。マーク・ベイカーは、「回転数の“高さ”よりも“安定性と一貫性”こそが重要だ」と説きます。ここでは、一般的な回転数の目安と、それにまつわるボウリング理論、そして実践的なアプローチを詳しく解説します。
◆ 回転数(Rev Rate)とは?
Rev Rateとは、1分間あたりの回転数(Revolutions per minute:RPM)を意味し、一般的には1投中にボールがレーン上で何回転しているかを元に、計算されます。ボウラーの手首や指、そしてタイミングによって生み出されるこの回転は、次のような効果をもたらします:
フックの幅が大きくなる
入射角が鋭くなり、ピンアクションが強くなる
ミスヒットでもピンが倒れやすくなる(ピンキャリーが良くなる)
◆ 一般的な回転数の目安(右投げ・片手投げの場合)
| ボウラータイプ | 回転数(RPM) | 特徴 |
|---|---|---|
| 初級者 | 150〜250 | 回転が少なく、ボールはあまり曲がらない |
| 中級者 | 250〜350 | ストライクが安定して出るレベル |
| 上級者(競技志向) | 350〜450 | フックと入射角がしっかりあり、コントロールも伴う |
| ハイレブ(高回転)ボウラー | 450〜550以上 | 曲がり幅・ピンアクションが大きく、リスクも高い |
マーク・ベイカーは、「回転数400以上が出せていれば“高回転”と呼べる範囲」とし、さらに「450以上になれば“非常に高回転”と評価される」と定義しています。
◆ ツーハンドの場合は別枠
両手投げ(ツーハンド)スタイルは構造的に高回転を生み出しやすく、600〜700RPMを超える選手も珍しくありません。世界最高峰のツーハンドボウラー、ジェイソン・ベルモンテ(Jason Belmonte)などは、公称で600RPMを超えるとされます。
ただし、ここでもマークは強調します:
「回転が高いことが、必ずしも“良いボウラー”というわけではない。」
◆ なぜ“安定した回転数”が重要なのか?
高回転数が生むフックの大きさは確かに魅力的ですが、同時にラインの再現性やコントロールの難しさも増すため、メリットとデメリットが紙一重になります。
一方で、例えば330RPMで安定した回転が毎投出せるボウラーは、スコアメイクが非常に安定しやすく、実戦では高いスコアを残す確率が高くなるのです。
マークはこの点について次のように述べています:
「毎回450RPMを出せる必要はない。毎回同じ“350RPM”を出せることの方が、圧倒的に価値がある。」
◆ 自分の回転数を知る方法
ボウリング場のモニター(SPECTO・Clutchなど)
高性能なセンターには、回転数を自動表示するシステムが設置されている
スマートフォンアプリ+ビデオ解析
ハイスピード撮影を行い、1秒間に何回転しているかを目視で確認
アプリ:「RevCounter」「MotionScope」など
プロショップでの測定
ドリル前後の回転特性を分析するサービスを行っている店舗もある
◆ 高回転数を目指すべきか?
ボールが曲がりやすくなり、ストライクが出やすくなる…と聞けば、「回転数をもっと上げたい!」と感じる方も多いでしょう。しかし、マークはそこにも冷静な見解を持っています。
| 高回転を目指すべき人 | そうでない人 |
|---|---|
| 高速リリースに自信がある | 安定したライン重視の人 |
| コントロールに自信がある | リリースの一貫性を重視したい人 |
| 大会でパワー勝負をする | スペアメイクを重視したい人 |
◆ 高回転を安定させるためのアドバイス(マーク・ベイカー流)
グリッププレッシャーを一定に
握り込みが強くなると、回転が乱れやすくなる
リリースのタイミングを“自然に”
指で“引っかけよう”とすると回転は不安定に
スイングに従って、自然なタイミングで離すこと
スイングを体幹に乗せる
上半身のひねりや無理な回転動作ではなく、「脚と腰の流れ」で回転を生む意識
24. ボールスピードアップのドリルはある?
「もっと速くボールを投げたい」「ボールスピードが遅くてレーンに負けてしまう」——これは非常に多くのボウラーが抱える共通の悩みです。特に回転はしっかりかかっているのに、スピード不足のために早めにボールが曲がってしまい、ポケットに届かないという場面はよく見られます。
そんな中、マーク・ベイカーはこの問題に対して意外な答えを出しています。
「正直に言うと、ボールスピードを“単独で上げるためのドリル”は存在しない。」
一体どういうことでしょうか? ここではマークの考え方を掘り下げつつ、**実際にスピードを上げるために“何をするべきか”**を、理論と実践に分けて詳しく解説していきます。
◆ スピードは“3つの要素”で決まる
マークは「ボールスピードはドリルでどうにかなるものではない」としながらも、スピードに関与する3つの重要な要素を提示しています:
体格(体の大きさ・質量)
体が大きければ、それだけ自然にボールに“推進力”を加えやすい
スイングの長さ
スイングが大きく、後方に十分に振り切れていれば加速が生まれる
フットワークの速さ
助走中の足のスピードが速ければ、そのぶんスイングにも加速がつく
つまり、スピードを上げるには「体の動き全体を見直す必要がある」というのがマークの持論です。
◆ 「スピードアップ=フォーム全体の再構築」へのアプローチ
ここからは、スピードを上げるために意識すべきポイントを実践的に紹介します。
✅ 1. スイングの“長さ”を最大化する
チェックポイント
バックスイングがしっかり耳の高さ、またはそれ以上まで振り上がっているか?
振り下ろしの際に「トップで止まらず、滑らかに加速」できているか?
練習方法
スイングオンリードリル(ボールを持ってその場で前後スイング)
低速スイング練習(助走なしでスイングの振り幅を意識)
✅ 2. 足のテンポを速くする
チェックポイント
最後の2歩(特にスライド前)の足の速さが一定か?
ゆっくり歩いていないか?(スイングとのタイミングがズレていないか?)
練習方法
テンポアップ練習:一定のリズムで「1、2、3、4…」とカウントしながら助走
スライド強化ドリル:最後の一歩を速く踏み込んでスピードを活かす
✅ 3. “投げない”練習でリズムを作る
マークの特徴的な指導法の一つに、「投げずに投球練習する」があります。
ステップ+スイングだけの繰り返し
ボールを実際に投げる前に、助走とスイングだけを10回繰り返す
これにより“足の速さとスイングの連動”が自然に身につく
フォームテンポの録画チェック
自分の助走テンポとスイングテンポを動画で確認し、プロと比較
◆ ボールスピードアップを邪魔する“NG行動”
| よくある誤解 | 結果 | 修正方法 |
|---|---|---|
| 腕に力を入れて投げる | フォームが崩れ、回転やコントロールが悪化 | スイングは脱力・振り子を意識 |
| 速く歩くだけでスピードを出そうとする | タイミングが狂ってリリースミスが増える | 足とスイングのテンポ一致を優先 |
| 短い助走でスピードを出そうとする | 助走の“加速”が不足 | 歩幅を広く、特に最後の2歩に勢いを持たせる |
◆ スピードアップは“全身の使い方の改善”で実現する
マーク・ベイカーの結論は明快です:
「スピードアップは“ドリル”ではなく、“体の使い方の改善”で得られるものだ。」
つまり、足の速さ・スイングの長さ・フォームのタイミングを見直せば、自然とスピードは増していきます。そして何よりも重要なのは、「スピードが上がっても、リリースや方向性が崩れないこと」。この“バランスの維持”がボウリングにおけるスピードアップの真のゴールです。
25. ファウルラインを見て狙うのはアリ?
「ファウルラインを見ることでターゲットを取っているんですが、これは正しいんでしょうか?」——ボウリング愛好者の中でも意見が分かれるこの問いに対し、マーク・ベイカーは次のように答えています。
「もしそれでストライクが取れているなら、“アリ”だ。ただし、私は教えない。」
これは、フォームや視線に関する非常に重要な議題であり、ボウリングの基礎からプロレベルのスタイルまで深く関係するテーマです。ここでは、ファウルラインを見ることのメリット・デメリット、プロの実例、そしてマークの考え方まで、網羅的に解説します。
◆ そもそも「ファウルラインを見て投げる」とは?
通常、多くのボウラーはファウルラインから約15フィート先(約4.5メートル)にあるアローや、その先のスパーをターゲットに設定します。しかし一部のボウラーは、足元にあるファウルラインやドット(立ち位置のマーク)を目線のターゲットとするスタイルをとります。
これは、非常に近い距離で視線を固定する投球方法であり、「視認性が高い」「スイングの一体感を作りやすい」などの利点もある一方で、「姿勢や体の傾きに悪影響を与える」可能性もあるスタイルです。
◆ ファウルラインを見ることのメリット
目標との距離が近く、狙いやすい
初心者が視線を固定しやすく、安心感がある
自分のステップとリリースの一致が分かりやすい
ドットやファウルラインとの距離を確認することでフォームの安定に役立つ
一部のトッププロにも成功例がある
女子プロのレジェンド、リズ・ジョンソンはファウルラインを見るスタイルで長年活躍
男子プロのウェス・マロットもこの視線スタイルを取り入れていることで知られている
◆ デメリットとリスク
マーク・ベイカーがこのスタイルを「推奨しない」としているのは、以下のような理由からです:
姿勢が前に傾く
視線を下に向けることで、頭が下がり、上体が前のめりになる
これによりリリース時の肩の動きが制限され、回転が不安定になる
肩と腕の使い方が変わってしまう
頭が下がることで、腕を“押し出す”形になりやすく、自然なスイングが損なわれる
視野が狭くなり、ダウンレーンの変化に気づきにくい
オイルのブレイクポイントやピンの動きを把握するのが難しくなる
マーク自身は6フィート4インチ(約193cm)の長身であるため、ファウルラインを見ると頭が大きく下がってしまい、投球に大きな悪影響が出ると語っています。
◆ 成功例はあるが、あくまで例外
リズ・ジョンソンのように、ファウルラインを見るスタイルでも世界トップの成績を収めている選手は存在します。ただし、これは**“その人の体格とスイングに合っているから可能な方法”**であり、万人に合うスタイルではないという点を忘れてはなりません。
マークは自身の経験から、「自分にできないスタイルは指導しない」という方針を持っています。これは、選手が再現性の高いフォームを身につけるために、自身の身体特性に合った方法で教えることを優先するという、極めて現実的な指導哲学です。
◆ あなたにとって「ファウルラインを見る」がアリかの判断基準
| 判定項目 | 内容 | 判定の目安 |
|---|---|---|
| 姿勢 | 頭が大きく前に出ていないか? | 前傾が強すぎるとNG |
| フォームの再現性 | 毎回同じリリースとラインで投げられているか? | 一貫性があるならOK |
| 精神的な安心感 | 狙いやすく、集中しやすいか? | 精度が上がるなら採用も可 |
| 成績への影響 | ストライク率、スペア率がどうか? | 数字が上がっているなら継続 |
◆ 練習での工夫
アロー視線とファウル視線の比較練習
同じ立ち位置からアローとファウルラインをそれぞれ見て投球し、結果を比較する
頭の傾きチェック(動画)
ファウルラインを見るスタイルで投げた時と、通常の視線で投げた時を撮影して、姿勢の変化を確認
短距離ターゲットの移行練習
ファウルライン → ドット → アロー → スパー へと、徐々にターゲットを遠ざけていくことで、スムーズな視線移行が可能になる
🎳 まとめ:すべてのボウラーに贈る言葉(マーク・ベイカーの教えを通じて)
ボウリングは、単なるスポーツ以上のものです。それは、「自分の体と向き合う時間」であり、「精度と再現性を追求する旅」であり、そして何より「失敗を成長に変える、無限の可能性を持った競技」です。
マーク・ベイカーは、25項目にもわたるアドバイスの中で、一貫して次のようなメッセージを私たちに伝えてくれています。
◆ ボウリングは“身体の仕組み”を理解するスポーツ
「うまく投げられない」——その原因は、感覚的な“下手さ”ではありません。それは単に「あなたの身体が正しく機能していないだけ」。スイングが乱れるのも、フォームが安定しないのも、回転やスピードが一定しないのも、すべて身体の使い方に理由があります。
マークはこう語ります:
「プロとアマの違いは、プロが“身体を使って投げている”のに対し、アマは“身体に逆らって投げている”ことだ。」
この言葉は、どんなレベルのボウラーにも響く本質です。
◆ 成功の鍵は“一貫性”にある
ストライクを取ることよりも、「毎回同じ動きができること」の方が、はるかに重要。回転数が400だろうと500だろうと、毎回バラバラなら意味がありません。逆に、毎回同じ350RPMで投げられるなら、それは強力な武器になります。
つまり、「自分の型」を知り、それを守り抜くことが、ボウリングにおける最大の戦略であり、最強のスキルです。
◆ 誰でも「変われる」——年齢も経験も関係ない
マークのセッションには、ジュニアからシニアまで、初心者からプロ志望者まで、幅広い層のボウラーが訪れます。その中で彼が一番大切にしているのは、「変わろうとする意志」です。
年齢も経験も関係ありません。今よりも少し上手くなりたい、もっと楽しみたい、もっと知りたい——その思いさえあれば、あなたはいつでも進化できます。
◆ 失敗は“フィードバック”でしかない
1ゲーム目が悪かった? ストライクが続かない? 10ピンが何度も残る?
そんなときこそ、マークのこの言葉を思い出してください。
「期待値を下げて、9を取ってスペアを取れ。それがリズムを呼び戻す第一歩だ。」
スコアに囚われすぎず、「ポケットを何回連続で突けるか」「スペアをどれだけ確実に取れるか」——そういった“技術の再現性”に集中すれば、スランプも必ず抜け出せます。
◆ ボウリングは「知性のスポーツ」でもある
レーンの読み方、ボールの選び方、ラインの取り方、メンタルの整え方…ボウリングは、“知識と戦略”が結果に大きく影響するスポーツです。
マーク・ベイカーのアドバイスはすべて、「感覚ではなく、理論で考えること」の重要性を教えてくれています。
🌟 最後に:あなたは“あなたのスタイル”でいい
マークは決して「この形が正解だ」と押し付けることはありません。むしろ彼が伝えたいのは、「あなた自身に合った投げ方を見つけよう」ということ。
まっすぐ歩けるならそれが正解
同じ回転が出せるならそれが正解
自信を持って投げられるフォームなら、それがあなたの正解
ボウリングは、誰かのスタイルを真似るだけではなく、「自分のスタイルを確立する旅」です。