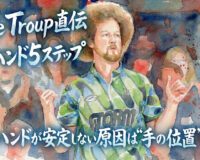ボウリング上達の鍵!
マーク・ベイカーが語る12の重要ポイント
記事に入る前に、音声による要点解説をお聞きいただくと、内容が一段と理解しやすくなります。
要点音声解説
本要点音声解説は、「The Clean Up Crew」掲載の動画内容を整理・補足して、NotebookLM を用いて生成したものです。
アメリカの有名コーチ、マーク・ベイカー氏が語った実践的なアドバイスから、初心者から上級者まで役立つ12の重要ポイントをピックアップしました。今日からの練習にすぐに役立つ内容を、ぜひチェックしてみてください。
1. ボールはリリース時に足元近くで離す
正確なボウリングを実現するうえで、ボールをどこでリリースするかは非常に重要です。特に注目したいのは、スライド足とボールの距離。多くのボウラーが陥りがちなミスが、リリースポイントが足元から離れすぎていることです。
マーク・ベイカー氏によれば、「スライド足の止まる位置からボールを10〜12枚も離してリリースするのは、かなり遠すぎる」とのこと。理想的なリリースポイントは、足首のすぐ近く、具体的には2〜3インチ(約5〜8センチ)以内。最大でも6インチ(15センチ)以内にとどめるのが望ましいとされています。
なぜこれが重要なのかというと、リリース位置が遠くなると、リリース角度やタイミングの再現性が下がり、結果として「狙ったラインに正確に投げる」ことが難しくなるからです。特に、オイルパターンが複雑なスポーツコンディションでは、わずかなズレがボールの挙動に大きな影響を与えます。
また、リリースが遠いと「投げる」という動作に余計な力が入りがちになり、手首や肩への負担も増え、長期的にはケガのリスクにもつながります。逆に、足元でスムーズにボールを置くようにリリースできれば、肩や腕の余分な動きが減り、自然なスイングで安定感が増します。
練習方法としては、自分のリリースポイントをビデオで確認するのが効果的です。スライド足の停止位置と、実際にボールが着地する場所の距離を見て、理想的な範囲に収まっているか確認しましょう。目安として、ボールがリリース後に着地する位置がスライド足の直線上または少し前であることが望ましいです。
足元でリリースする感覚を掴む練習ドリルとしては、1ステップ・リリースドリル(1歩だけの助走でスイングからリリースまでを練習する)が効果的です。スイングの軌道が安定し、足元での正確なリリースが身につきやすくなります。
足元リリースは、ボウリング全体の安定性と精度を左右する基礎中の基礎。初心者だけでなく、上級者も定期的にチェックしておきたいポイントです。
2. ボールが指穴の上を転がるのはリリースのタイミングミス
ボウリングにおいて、ボールが転がる際に指穴(フィンガーホール)の上を通る現象を見たことはありませんか?これは一般的に「ミスリリース」の一種で、意図しないスピンや曲がりの不安定さを引き起こす原因になります。
マーク・ベイカー氏によると、ボールが指穴の上を転がってしまう原因は「手首の回転が早すぎること」にあります。つまり、回転をかけようとする意識が強すぎて、ボールのリリース前に手がすでに外側に回ってしまっているのです。このような早すぎる手首の動きは、いわゆる「手でこねる」動作につながり、結果的に指穴の上にボールが乗るような転がり方になります。
本来、ボールに回転を与えるべきタイミングは「スイングの最下点」、つまり足元でリリースする瞬間です。そのときに手首をしなやかに動かしながら、自然なフィンガーリフト(指でボールを弾くような動き)で回転を加えるのが理想です。
この「回転の遅らせ方」を身につけるためには、まず「手の平ができるだけ長くボールの下に残る感覚」を大事にしましょう。手のひらが早く外側に開くと、リリース前にボールが傾き、真っ直ぐな回転軸を失ってしまいます。結果的に、ボールが意図したラインを外れたり、ピンアクションが弱くなったりします。
さらに、ベイカー氏は「回転を加えるタイミングは2か所しかない」とも述べています。一つは「かかとの前(アプローチの初期段階)」、もう一つは「つま先の前(リリース直前)」。当然ながら、正しいのはつま先の前でのリリースです。早すぎるタイミングで回転を入れると、結果としてボールの軌道が不安定になります。
効果的な練習方法としては、「後方からのビデオ撮影」でリリース時の手の動きをチェックすることです。指穴の真上を転がる軌跡が頻繁に見られる場合は、回転をかけるタイミングを見直す必要があります。また、ボールにテープを貼って回転軸を視覚化する方法もおすすめです。真っ直ぐなラインで回転していれば、適切なリリースができている証拠です。
初心者や中級者は「フックをかけたい」という思いから、無意識に早く手を返しがちですが、それが逆効果になるケースも多々あります。まずは「遅れて回す」「手首を最後まで我慢する」意識を持ちましょう。これができれば、ボールの回転軸が安定し、より再現性の高い投球へとつながります。
ボールが指穴の上を転がる現象は、スイングの技術不足ではなく「リリースタイミングの乱れ」に原因があります。タイミングを整えることで、精度もピンアクションも大きく改善されるはずです。
3. 遅く投げたいときは「前に立つ」
ボールスピードを調整したい場面、特にスポーツコンディションやショートオイルパターンでのプレーでは「意図的に遅く投げる」必要が出てきます。多くのボウラーがやってしまうのが、歩くスピードを意識的に遅くして、ボールスピードを落とそうとする方法ですが、これは逆効果になりやすいのです。
マーク・ベイカー氏は「体の動きを遅くするのではなく、スタート位置を前にずらすべき」と強調しています。なぜなら、ただ歩みを遅くするだけではスイングも減速してしまい、結果的にリリース時のタイミングが乱れて、フォーム全体のバランスが崩れてしまうからです。
たとえば、普段より6インチ(約15センチ)前からスタートするだけで、歩幅はそのままに、全体の助走距離が短くなります。これにより、体の「ギア比」、つまり下半身とスイングのタイミングのバランスを維持したまま、スピードだけを落とすことができるのです。目安としては、「時速1マイル(約1.6km/h)落としたいなら6インチ前に立つ」と覚えておくとよいでしょう。
これは、プロボウラーが実際に使っているテクニックでもあります。たとえばクリス・バーンズは、状況に応じてアプローチの一番後ろから投げることもあれば、前方から3歩助走で投げることもあります。これはまさに「スピード調整のための位置調整」であり、歩くスピードそのものを変えてはいないのです。
また、もう一つのメリットとして「スイングが一定に保たれる」点が挙げられます。フォームの安定性と再現性が向上し、思い通りのラインでボールを転がせるようになります。特にウレタンボールを使用する際や、ショートオイルでの早めのフッキングが求められる場面では、このテクニックが大いに効果を発揮します。
逆に「速く投げたい」場合についても言及されていますが、ベイカー氏は「後ろに下がる」ことはあまり推奨していません。理由は、スタート位置が後ろになりすぎると、ピボットステップ(踏み込み足)がファウルラインから遠くなり、無理な踏み込みや体の前傾が強まり、結果的にリリース時に力みが出てしまうからです。
実践的な練習方法としては、アプローチにマーカーを置いて、6インチ・12インチ・18インチごとの立ち位置から投球してみるドリルが効果的です。スピードとタイミングの関係を身体で覚えることで、状況に応じた調整力が身につきます。
スピードコントロールは、ストライク率やスペアの安定性を高めるために欠かせないスキルです。その第一歩として「前に立つ」というシンプルな戦略をぜひ取り入れてみてください。
4. 「空気を前に動かす」感覚を意識せよ
「空気を前に動かす」という表現は、マーク・ベイカー氏が独自に使っている非常にユニークな理論ですが、実は多くのプロボウラーや上級者が無意識に実践している、安定したリリースとバランスを生むための非常に重要な感覚です。
この言葉の意味を理解するには、まず「タイミングスポット(リリース直前の体の位置)」を明確にする必要があります。タイミングスポットとは、左足(右投げの場合)がスライドし、頭がその前方に位置し、スイングが体の真横から前方に向かう瞬間を指します。このとき、あご(顎)と膝の距離に注目してください。
マーク氏が言う「空気を前に動かす」とは、このあごと膝の距離をリリースまで一定に保つことを意味します。つまり、頭を必要以上に上下させたり、体を傾けたりせず、安定した重心のまま前方に向かってスイングと体の流れを作っていくイメージです。
これができると、スイングの「フラットスポット(ボールが前方に向かって水平に移動する短い区間)」が生まれ、結果的に安定したリリースと方向性を実現できます。このフラットスポットがあることで、リリース時の手の位置や回転量が毎回ほぼ同じになり、ラインの再現性が格段に向上します。
逆に、「空気を下に動かす」=頭がリリースに向けて前傾していくと、手がボールの上に乗ってしまい、トップスピンがかかってしまうため、スキッド(滑り)しづらくなり、ピンアクションも弱くなります。また、「空気を上に動かす」=頭が上がってしまうと、手がボールの下を離れすぎて、回転軸が崩れ、スピナーのようなリリースになってしまいがちです。
この「空気を前に動かす」感覚を養うためには、以下のような練習法が効果的です:
実践練習ドリル:フォーム固定ドリル
スライド足を出して、あごと膝の距離を意識しながらリリース直前の姿勢で静止。
そのままのバランスで、空のボール(もしくは軽い練習ボール)を前にリリース。
リリース後、姿勢が崩れなければ「空気を前に動かす」感覚が身についている証拠です。
また、動画を撮影して、自分のリリース前後の頭の高さや体の角度の変化をチェックするのも非常に有効です。安定して前方への流れが作れている人は、頭の位置がスムーズに前に進み、体幹の軸が大きくブレていません。
この感覚が身につくと、ラインの精度が上がるだけでなく、フォームの一貫性、タイミングの正確さ、さらにはバランスの良さまで自然と向上します。まさに、上達の核心をなす概念といえるでしょう。
「空気を前に動かす」――一見抽象的ですが、これができればあなたのボウリングは一段階上のステージへ進むことができるはずです。
5. 左足が静かなときはバランスが良い証拠
「静かな左足」という表現は、一見すると分かりにくいかもしれません。しかし、これはボウリングのリリースにおける「身体の安定性」と「バランスの良さ」を見極める非常に重要な指標です。
右投げの場合、最後にスライドするのは左足です。この左足が、ボールをリリースした直後も地面にしっかりと接地し、ぶれずに安定している状態を「静かな左足」と呼びます。マーク・ベイカー氏は、この左足が静かであることが、「正しいスイングとリリースの結果」であり、バランスが整っている証拠だと述べています。
では、なぜ左足が動いてしまうのでしょうか?その原因の多くは、上半身(特に肩)でボールを「投げよう」としてしまうことにあります。つまり、自然なスイングではなく、力で押し出すようなフォームになっていると、体全体が前傾しすぎたり、頭が前に出たりして、結果的に左足がぐらついたり、ずれてしまいます。
一方、「左足が静かに止まっている」時というのは、スイングが主導し、肩に余計な力が入っていない状態です。体の軸がしっかりと保たれ、リリース時に頭も上下せず、滑らかに前方に進む動作ができている証です。このとき、頭の位置もブレず、リリース直後からフィニッシュまでの姿勢が非常に美しく安定しています。
このバランスは、再現性の高い投球フォームを作るうえで非常に重要です。プロボウラーの試合映像をよく観察するとわかりますが、上級者ほど左足がほとんど動かず、リリース後もピタッと止まっていることが多いです。それは彼らのスイングが自然で、体の中心(コア)を使ったバランスの取れた投球ができているからです。
バランスチェック方法(ドリル)
スローで投球練習を行い、ボールをリリースした直後に2秒静止する。
このとき、左足が動かず、頭も上下していなければバランス良好。
逆に、左足が横に流れたり、身体が傾いたりしている場合は、肩に力が入っていたり、リリースがスイング主導で行えていない可能性があります。
また、ビデオで自分のフォームをチェックするのも有効です。スローモーションで左足の動きを観察し、投球後にバランスが崩れていないかを確認しましょう。安定してピン前に立っていられるフォームこそ、プロレベルに近づくための第一歩です。
左足の静かさは、ボウリングにおける「最終結果の鏡」。ここが乱れていると、いくらスイングやリリースがよくても、結果にブレが出やすくなります。逆に、静かな左足があるなら、あなたのフォームはすでに高い完成度に近づいている証拠です。
6. 「サージ・イースターグリップ」とは
「サージ・イースターグリップ(Sarge Easter Grip)」は、一般的なフィンガーグリップとは異なる、少し特殊で高度なグリップスタイルの一つです。使いこなすにはやや専門的な理解が必要ですが、高いレベルでボールコントロールを目指すボウラーにとっては一考の価値がある技術です。
サージ・イースターグリップの構造
このグリップでは、中指(ミドルフィンガー)をフィンガーチップ(第一関節まで挿入する一般的なスタイル)にし、薬指(リングフィンガー)をコンベンショナル(第二関節まで挿入する古典的スタイル)にします。
このように、左右の指で異なる深さの挿入方法をとることで、リリース時に指にかかる力のバランスが変化します。通常のフィンガーチップグリップでは、指全体で均等に引っ掛けて回転をかけるのが基本ですが、サージ・イースターグリップでは中指により強いプレッシャーがかかり、回転軸を安定させる効果があります。
なぜこのグリップを使うのか?
このグリップが生まれた背景には、「回転数の多いボウラーが、過剰なリリースを抑制してコントロールを高める」目的があります。たとえば、ロバート・スミスやマイケル・フェイガン、マイク・ディニーといった、非常に高いレベルの回転力を持つプロボウラーたちがこのグリップを採用していたことで知られています。
高回転ボウラーは、時にフックが過剰になり、ボールが早くブレイクしすぎたり、ラインの再現性が乱れる傾向があります。サージ・イースターグリップは、薬指側の回転力を意図的に制御することで、「ほどよいフック」と「安定した軌道」を両立させるための手段として利用されています。
メリットとデメリット
メリット:
回転数が高すぎるボウラーにとって、フック量を抑えられる。
リリース時の引っかかりが自然になり、回転軸が安定する。
高速回転でもピン前での動きが読みやすくなる。
デメリット:
指の使い方が特殊なため、慣れるまで違和感が強い。
指の負担がアンバランスになりやすく、長期的にはケアが必要。
一般的なフィンガーグリップよりも調整に時間がかかる。
誰に向いているか?
このグリップは、すでに一定の技術と回転力を持ち、ボールのコントロールをより細かく調整したい上級者に向いています。逆に、回転が少ない初心者や中級者がこのグリップを試しても、フックが弱くなりすぎて逆効果になる場合があります。
実践アドバイス
サージ・イースターグリップを試す際は、必ずプロショップでフィッティングを受けることをおすすめします。通常のグリップとは掘り方や角度が異なるため、独自の計測とドリル技術が必要です。また、最初は軽めのボールで、低速からフォームに慣れる練習を重ねましょう。
「サージ・イースターグリップ」は決して一般的ではありませんが、ボールの動きをコントロールするうえで選択肢の一つとして知っておく価値があります。自分のスタイルと目的に合わせて、最適なグリップを選ぶことが、上達への近道です。
7. 「バランス」はフォロースルーで判断する
ボウリングにおける「バランス」とは、投球動作中に身体の軸が安定し、力を無駄なく伝えられる状態を指します。特にリリース後のフォロースルー(投げた後の腕と体の動き)は、そのバランスの良し悪しを如実に表す重要な指標です。
マーク・ベイカー氏は、「フォロースルー中にふらついたり、体勢が崩れたりするのは、スイングのタイミングがズレている証拠」だと述べています。逆に、ボールをリリースした後もスムーズにフォロースルーが完了し、体勢が安定しているなら、バランスが正しく保たれていたという証拠です。
フォロースルーのどこで判断するのか?
判断のポイントは、「ボールがレーンのアロー(目印)を通過した後、体の姿勢がどうなっているか」です。具体的には:
リリース直後に右足(右投げの場合)が自然に後方へスイングして着地する
上体が前傾しすぎたり、横に倒れたりしていない
頭の位置がリリース前後で大きく変化していない
肩のラインが開きすぎず、ターゲット方向に向いている
こうした状態であれば、スイング、ステップ、リリースのタイミングがしっかり噛み合っていると判断できます。
一方で、ボールがアローを過ぎる前に体が大きく傾いたり、右足がバランスを取るように不自然に出ている場合は、「リリースに無理があった」可能性が高く、フォームの再現性に課題があるというサインです。
「ステップオフ」と「フォールオフ」の違い
ベイカー氏は、バランスの崩れには2種類あると説明しています:
ステップオフ(Step-off)
→ リリース後、バランスを保ったまま右足が自然に横に流れる動き。これは「見た目の変化」であって、バランスが崩れているわけではない。フォールオフ(Fall-off)
→ リリース直後、上半身が崩れたり、フォロースルーが途中で止まってしまい、右足が急激に出たり、ふらついたりする動き。これは「明確なバランス崩壊」であり、タイミングやフォームの修正が必要です。
ベイカー氏は、「ボールがアローを通過し、ブレイクポイントへ向かっている時点でフォロースルーが完了していれば、その後にどんな動きがあっても影響は少ない」と述べています。極端な話、「ボールが手を離れてからバク宙しても問題ない」とも(笑)。
つまり、フォロースルーが途切れずに最後まで振り切れるかどうかが、最も重要なのです。
実践練習ドリル:フォロースルーチェック
撮影機器(スマホ等)をレーン後方に設置し、投球後のフォロースルーを録画。
ボールがアローを通過するまでの体の動きをスローモーションで確認。
フォロースルーが途中で止まっていたり、頭や肩の位置が崩れていないかをチェック。
もし安定してフォロースルーできていない場合は、スイングの始動タイミングや助走のテンポを見直しましょう。特にリリース直前で体が焦って前のめりになっていないかが、最大のチェックポイントです。
バランスとは、リリースの一瞬だけではなく、投球動作全体の流れが正しく保たれていたかどうかを、フォロースルーで確認する作業です。この視点を持つだけで、あなたのフォーム分析と改善は格段に精度を増すでしょう。
8. フォロースルーで右腕が外に流れる問題
フォロースルーは、ボールが手を離れた後の腕と体の動きですが、その軌道には投球全体のクセや問題点が如実に表れます。中でもよく見られるのが、右投げのボウラーがフォロースルーで右腕が外(右側)に流れてしまう現象です。この動きは、一見すると自然に見えるかもしれませんが、再現性と精度を追求する上では大きな課題となることがあります。
なぜ右腕が外に流れるのか?
マーク・ベイカー氏はこの問題に対し、「腕の流れ方よりも、肘の向きに注目すべき」と述べています。腕が右側に流れてしまう原因として、以下の要因が考えられます:
肘が体の正面を向いていない
→ フォロースルー時に肘が外を向くと、自然と手の平が開き、ボールにかける回転軸が外れてしまいます。体の開き(肩や胸)が早すぎる
→ リリースの直前に上半身が目標方向よりも早く開いてしまうと、スイングが外側に引っ張られ、右腕が外に抜けやすくなります。狙い(ターゲット)に正対できていない
→ リリース時にベルトのバックルや胸(胸骨)がターゲットに向いていないと、体の回転が左右にブレやすくなります。
これらの要素が複合すると、リリース後に右腕が本来の軌道より外側に流れ、「押し出すフォーム」や「手で操作するスイング」になってしまいがちです。
理想のフォロースルーとは?
理想的なフォロースルーでは、肘が身体の正面から上に伸び、手のひらが目標方向またはやや内側を向くフォームが一般的です。プロボウラーの多くは、リリース後の腕が頭の横からまっすぐ上方向に抜けていくような動きになっています。これは、スイングの軌道が真っすぐ目標に向かっており、ボールが軸ブレなく転がるための基本でもあります。
とはいえ、必ずしも全員が同じ動きをしているわけではありません。たとえば、ジェイソン・ベルモンテのような高回転ボウラーは、フォロースルーがやや右側に抜ける傾向がありますが、それでも彼のフォームは安定し、リリースとスイングのバランスが取れています。大切なのは、「見た目」よりも、「狙ったラインに対して正確に投げられているか」ということです。
実践的な改善法
1. 肘の向きを意識したスロー投球練習
→ ゆっくりとした助走で、肘が常に正面に向いたままスイングできているかを確認します。
2. ベルトと胸の向きを揃えるドリル
→ リリース時にベルトのバックルと胸骨(胸の中央)が狙いのラインに向くよう、ミラーや動画でチェック。
3. タオルスイングドリル
→ 軽いタオルを持ってスイング練習を行い、腕が自然に前へと振り切れる感覚を養います。
4. 投球後の姿勢静止
→ 投げた後に3秒静止し、自分の腕が正面に向いているか確認する習慣をつけることで、無意識の修正が可能になります。
腕が外に流れる問題は、体のバランスやタイミング、スイング軌道のズレを知らせてくれる「フォームの警告灯」とも言えます。見た目よりも「狙った場所にボールが行っているか」「安定した回転がかかっているか」を重視しながら、肘の向きや上半身の動きに注意を払うことで、より正確で再現性の高い投球フォームを手に入れることができるでしょう。
9. スペアは「自分だけのシステム」を作れ
ボウリングにおいて「スペアは地味」と思われがちですが、実際にはスコアを安定させるための生命線です。どんなにストライクが続いても、スペアを取りこぼせば一気にスコアは伸び悩みます。特に競技志向のボウラーにとっては、「スペアの確実性=強さ」と言っても過言ではありません。
「Baker Box」は存在しない、だからこそ「自分のルール」が必要
マーク・ベイカー氏は、「スペアにはBaker Box(万能の公式)は存在しない」と明言しています。つまり、すべての人にとって正解となるスペア攻略法はなく、自分の感覚・投球スタイル・癖に合わせたルール(システム)を作り、それを信じて練習し続けることこそが唯一の正解なのです。
たとえば、10ピン(右端のピン)を取る際の代表的な方法の一つに「30スタンス→センターアロー通過で10ピン」というシステムがあります。これはボウラー自身の投球角度、回転量、ボールの種類などに基づいた「自分なりのルール」によって成り立っています。
マーク氏は、自身のキャンプで複数のスペア攻略スタイルを紹介しています:
ダグ・ケント方式:ピンごとに角度とリリースを変える細かい調整型。
デイブ・ヒュースタッド方式:アグレッシブなライン取りで左右の幅を少なく保つ。
ロビン・ロメロ方式:ウレタンやリアクティブも駆使した柔軟な対応。
マーク・ベイカー方式:基本はストライクラインからのアジャストによるスタイル。
このように、プロでもスペアへのアプローチは千差万別です。つまり、「これが正解」という型は存在せず、自分に合ったルールを作り上げることが、最も重要なのです。
自分のスペアシステムを作る手順
自分の標準的な投球ラインを知る
→ 例えば「立ち位置20枚目→10枚目を通す」でストライクラインなら、それを基準に考えます。各ピンに対する“成功率の高い”狙い位置を記録する
→ 例:「7ピンはスタンス36枚目→4枚目通過」「3-6-10は25枚目→15枚目通過」など。素材に合ったボール選択
→ レーンコンディションやオイルパターンによっては、スペア用にプラスチックボールを使うのが有効です。回転が抑えられ、狙った通りにまっすぐ転がるからです。特にスポーツコンディションではこの選択が効果的。毎回の失敗を記録し、微調整する
→ スペアが取れなかったときの「立ち位置」「通過したスパット(目標点)」「投げたボールの種類」を記録し、傾向を把握することで、自分のルールがどんどん精度を増していきます。
なぜ「自分だけのシステム」が必要なのか?
感覚では限界があるから:投球において「なんとなくこの辺りを狙う」では、緊張時やコンディションの変化に対応できません。
プロも“反復”で成り立っているから:トップレベルのプロボウラーですら、毎回同じ場所に立ち、同じラインを通し、同じようにスペアを処理しています。これは「感覚」ではなく「システム」に基づいた行動です。
安心感と集中力の確保:自分なりの明確なルールがあれば、試合中に余計な判断を減らし、メンタルの消耗を防ぐことができます。
スペア処理において最も大切なのは、「正解」を探すことではなく、「自分の型」を作ってそれを信じることです。ひとたびそのシステムが固まれば、あなたのボウリングは格段に安定し、スコアは自然と伸びていくはずです。
次にスペアを外したとき、落ち込むのではなく、「自分のシステムに何か調整が必要か?」と考える。そんな姿勢こそが、上達への第一歩です。
10. 目標点は足と一緒に動かす
多くのボウラーが「足の位置だけを変えて、目線(ターゲット)をそのままにして投げる」というミスを無意識にしてしまいがちです。マーク・ベイカー氏はこの点に対し、「足を動かすなら、必ず目も一緒に動かすべき」と強調しています。
なぜ目標点を動かす必要があるのか?
ボウリングは、「スタンス位置(立ち位置)」「目標点(スパットやアロー)」「ブレイクポイント(ボールが曲がり始める地点)」の3点を一直線に結ぶラインを正確に通す」ことが求められます。立ち位置を左右にずらすだけで、目標点を変えなければ、そのラインがズレてしまい、思ったところにボールが届かなくなるのです。
たとえば、オイルが多くてボールが滑るようなコンディションでは、立ち位置を左にずらして角度を付けて投げる必要があります。その際に、目標点(スパット)も同じように左にずらさなければ、スイング軌道と体の向きが合わず、結果的にミスショットになってしまいます。
ベイカー氏の「目標点移動の黄金ルール」
マーク・ベイカー氏は、スタンスと目標点の動かし方にいくつかのルールを提案しています。代表的なのが以下の2つ:
2:1の比率ルール
→ 立ち位置を2枚動かしたら、目標点は1枚動かす。これは、斜めにラインを保ちながらブレイクポイントを維持するための最も基本的な考え方です。距離によって比率を変える
→ 立ち位置が遠いほど(たとえばボード30から投げるような広いライン)、目標点とスタンス位置の差は大きくなります。逆に、立ち位置が中央や右寄りの場合(ボード15前後)では、目標点との差は小さくなります。
具体例で理解するスタンスと目標点の関係
中央寄り(ストレート系)の投球
→ 立ち位置15枚目 → 目標点7枚目(差8枚)
→ 足と目の移動はほぼ同じペースで。外側からのフック系投球
→ 立ち位置30枚目 → 目標点15~17枚目(差13~15枚)
→ 足の移動量が目の移動より大きくなる。つまり、立ち位置が広がるほど「外→中」への角度が大きくなるため、目標点とのズレを広げる必要があります。
このように、「どのラインを通すか」によって、スタンスと目標点の関係は変わるのです。ただし大前提は、「スタンスが変わったら目線も必ずセットで変えること」です。
ドリフトやミスの傾向も把握せよ
ベイカー氏はさらに、「目標点とスタンスを変えるときには、自分の“ドリフト”と“ミスの傾向”も把握しておくべき」ともアドバイスしています。
ドリフト:助走中に自分がどの方向に何枚くらい横にズレるか。これを考慮に入れなければ、立ち位置と狙いが合っていても、結果的にズレてしまいます。
ミスの傾向:自分がどの方向に外しやすいかを知っておけば、目標点を微調整する際の参考になります。
たとえば、「自分は4枚ドリフトして3枚ミスする傾向がある」のであれば、それを前提に、立ち位置と目標点を調整する必要があります。
練習法:スタンス・ターゲット連動ドリル
各スタンス位置(20、25、30など)で立ち、通すべきスパットをノートに記録。
それぞれの位置でボールを10球ずつ投げ、どの組み合わせが最も安定しているか分析。
練習中にドリフト量も同時にチェックし、実際の投球におけるズレを数値化。
「目線は変えずに足だけずらす」は、初心者が陥りやすい典型的な落とし穴です。スコアが伸び悩む中級者こそ、この基本にもう一度立ち返ってください。足と目の連動を習慣化することで、狙ったラインに正確にボールを通せるようになり、ピンアクションも格段に安定します。
「足を動かすなら、目も動かす」――この黄金律を守ることが、上達への確実な一歩です。
11. ドリフトとミスを把握せよ
ボウリング上達のカギは「正確に投げること」だと考えられがちですが、実は「自分のズレを正確に把握して修正できること」こそが、安定したスコアに直結する最大の武器です。そのために必要なのが、「ドリフト」と「ミスの傾向」を正しく理解し、投球に活かすことです。
ドリフトとは何か?
ドリフト(drift)とは、アプローチ中に助走しながら、意図しない横方向の移動が発生することです。たとえば、スタンスで右足を15枚目に置いたのに、実際のスライド足(リリース時の左足)が18枚目に着地した場合、これは「3枚左にドリフトした」ことになります。
ドリフトは、個人の歩き方や体の重心移動、フォームのクセによって必ず何らかの形で起こります。大切なのは、それを「なくすこと」ではなく、「自分のドリフトを理解して、投球ラインに織り込むこと」です。
ミスとは何か?
ここで言うミスとは、「目標点に向かって正確にボールを通せなかった誤差」のことです。たとえば、「センターアロー(20枚目)を狙って投げたのに、実際には17枚目を通っていた」という場合、これは「3枚右にミスした」という意味です。
プロボウラーですら、完全に目標をトレースできるわけではありません。マーク・ベイカー氏自身も、「人生で一度も完全に目標をヒットしたことはない」と冗談交じりに語るほどです。重要なのは、「自分がどれくらい、どの方向にミスしやすいかを把握しておくこと」です。
ドリフトとミスを合わせて考える
以下のような具体的な数値例で考えると分かりやすくなります:
スタンス:16枚目
目標点:7枚目
ドリフト:左に4枚
ミス:右に3枚
この場合、スライド時の着地点は12枚目、実際に通ったのは10枚目という結果になります。狙った7枚目とは3枚ズレていますが、それでも「投球結果が安定している」なら、そのラインを基準にして投げるという判断も成り立ちます。
つまり、「立つ位置」だけでなく、「スライド位置」「実際の通過点」をすべて把握してはじめて、本当に正しいアジャストが可能になるのです。
上級者は他人のラインを自分に置き換えて読む
ベイカー氏は、かつてプロツアーでマーチャル・ホルマン選手のラインを参考にしていたそうです。ホルマンがスライドしていた位置と投球ラインを見て、自分のドリフトとミスを考慮しながら立ち位置と目標点を調整していたのです。
このように、「他人がどこを滑ってどこを通したか」+「自分のズレ」=「自分の立ち位置と目標点」という形で考えられるようになれば、ライン読みの精度が飛躍的に高まります。
練習法:ドリフト・ミス可視化ドリル
アプローチに目印テープを置き、スタンス位置とスライド位置を記録。
レーンのスパットを目標点に設定し、実際に通った場所をビデオで確認。
ドリフト量とミスの方向を記録し、自分の「平均的なズレ」を把握。
それを元に、ライン設定時に必要な補正値を計算。
「ズレ=悪」ではなく、「ズレ=個性」です。大切なのは、ズレに無自覚なまま投げ続けることではなく、そのズレをデータとして管理し、自分のボウリングに組み込むことです。
ドリフトとミスを正確に把握できるようになれば、あなたのライン取り、アジャスト力、スペアの精度、すべてが格段に向上します。プロレベルの安定感を手に入れたいなら、まずは「自分を知ること」から始めましょう。
12. 精神面の安定がすべての基礎
ボウリングの技術がどれだけ優れていても、精神面が不安定な状態では、その実力を発揮することはできません。これはレクリエーションでも競技でも同じです。マーク・ベイカー氏は、「ボウリングの上達において最も重要なものは、自信と冷静さ(calmness)である」と強調しています。
なぜ精神面が重要なのか?
ボウリングは、他の競技に比べて「静かな環境で、自分との戦い」が求められるスポーツです。投球ごとに時間があり、自分の思考と向き合う時間が長く、一球ごとのメンタル状態がパフォーマンスに直結するのです。
さらに、1ゲーム中に複数回訪れる「ここでストライクが必要」「このスペアを絶対に取らなければならない」といったプレッシャーの中で、動揺せずに自分のフォームを貫けるかどうかが勝敗を分けます。
ベイカー氏は、自分自身を「元アスリート」とし、「私はまず自信をつけることで、気持ちを落ち着けるタイプだった」と述べています。一方で、「質問で不安を解消し、頭を整理することで落ち着きを得るタイプの人もいる」とも言っています。
つまり、人それぞれに「自信が先か、冷静さが先か」の違いがあるということです。自分がどちらのタイプなのかを見極め、それに合ったメンタルの整え方を実践することが、安定したスコアと投球の鍵になります。
自信タイプと冷静タイプの見分け方
自信タイプ:
→ フォームやラインが明確で、「やれる!」という感覚があるときに高い集中力を発揮。練習で成功体験を積むことで力を出せる。冷静タイプ:
→ 質問や分析で頭の中をクリアにしておくことで、不安が消え、安心して投球できる。チェックリストやルーティンを重視する傾向あり。
どちらが良い悪いではありません。大切なのは、「自分はどちらのタイプかを知り、それに合わせた準備をすること」です。
実践的なメンタルトレーニング方法
ルーティンの確立
→ 毎回同じ動作(呼吸・構え・助走のリズム)を行うことで、脳に「安心していい」と信号を送る。緊張時こそルーティンが威力を発揮します。ポジティブセルフトーク
→ 「大丈夫」「このラインは何度も練習した」「狙い通りに投げればいい」など、自分に言い聞かせる言葉を習慣化。自信タイプにも冷静タイプにも有効です。視覚化(イメージトレーニング)
→ 成功する投球を頭の中で何度も描くことで、脳が成功の感覚を事前にインプットします。リリースの感覚やボールの曲がり方を明確にイメージすることが効果的です。失投の受け入れ練習
→ 完璧を求めすぎず、「1投のミスで崩れない」精神を育てること。たとえば、「ミスしたら次でリカバリーする」と決めておくことで、焦りを最小限に抑えられます。
上級者に共通するメンタルの特徴
一球ごとに「過去を切り離す」切り替えの速さ
緊張を力に変えるポジティブ思考
投球前の「静寂を楽しむ」集中力
自分のルーティンや準備への絶対的な信頼
こうしたメンタルの技術は、試合中だけでなく、練習中から意識することで徐々に身についていきます。フォームと同様、精神力も練習で鍛えられるものなのです。
スコアに波がある、ミスを引きずってしまう、緊張で手が震える……そんな悩みを持っている人は、技術よりもまず「自分の精神タイプ」を理解するところから始めましょう。
精神面の安定は、すべての技術の土台です。強い心は、強いショットを生み出します。あなた自身の「心の整え方」を見つけることで、ボウリングがもっと楽しく、もっと上達するはずです。